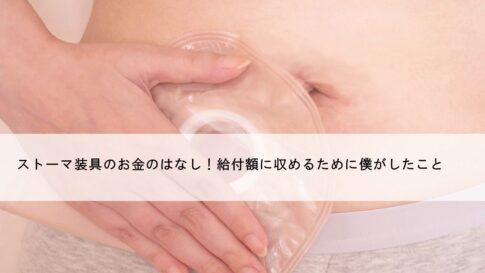もし、過去の自分に何か伝えることができるなら。
「この先、母親が要介護になって大変なことになるから、ストーマについて詳しく聞いておけ!」と言いたいです。
ストーマ保有者の親が、高齢になって要介護になったらどうなるのか?
そう考えれば容易に想像できそうなものですが、何の備えもしていなかった僕はなるべくして労力と費用を消耗しまくって散々な目に遭いました(-_-;)
今回は、このような失敗の経験から、親のストーマ介助で困ったことや知っておいたら役立ちそうなことをまとめましたので参考にしてみてください。
目次
最初に、親がストーマの管理が困難になったときを想定しておくことが大切です。
母が、要介護になって何が大変だったかと言うとストーマの介助。
もちろん、在宅介護をするために介護申請や「かかりつけ医」探しなど、慣れない手続きや作業は大変でしたが費やす時間と労力の桁が違います。
それにストーマの介助は、それなりに知識や慣れも必要です。
排泄介助(パウチに溜まった便を出す作業)に加えて、パウチ交換や給付の更新手続き、その他にも便モレ対策もしなければならないので、いきなりご家族が引き継ぐとなると相当厳しいかと思います。
ストーマの介助は、親が高齢になるにつれご家族の手助けが必要となるものとして、日ごろから話し合って情報を共有しておくことをおすすめします。
身体に合うパウチを見つけるには?
国内で流通しているメーカーは、僕の知る限り8社あります。
1つのメーカーの中にもたくさんの種類があるので、その中から自分にぴったりのパウチを探し出すには1つずつ地道に試さないといけないのが実情です。
入院中であれば、看護師さんが色々試してくれて退院までにメドをつけてくれると思います。
問題は、在宅のときです。
在宅でも、体重増減での体型の変化などでパウチが合わなくなることもあります。
そのようなときは、ストーマ外来がおすすめです。
ストーマ外来とは、その名のとおり「ストーマ(人工肛門・人工膀胱)ケア」「失禁(便や尿が漏れること)ケア」などに関するサポートを行う外来です。
そこには、皮膚・排泄ケア認定看護師 (WOCナース)という、ストーマケアのスペシャリストが在籍していて、退院後の生活やケア・管理方法などの相談や指導を行っています。
もし、寝たきりなどで通院が困難な場合は、訪問診療の医師や訪問看護師、ストーマ商品を購入している販売店で相談してみてください。
きっと力になってくれるはずです。
パウチの貼付期間は人それぞれ異なる
パウチは、長く貼り過ぎても短すぎても皮膚の炎症を引き起こす原因になるので、パウチの貼り替えどきを把握することが重要です。
一応、どのメーカーのパウチも貼付期間の設定はされていますが、例えば母の使用するパウチは4~7日となっており日数に幅があります。
これは同じパウチを使用していても、皮膚の状態、軟便や水様便など便の質や量、汗の量にも左右されるため、人それぞれ貼付期間が異なるからです。
ちなみに、母の貼付期間は4~5日といったところでしょうか。
貼付期間を見誤るとどうなるのか?
それでなくてもストーマ周辺の皮膚は、常にパウチを貼っているため皮膚トラブルになりやすい繊細な部分です。
貼付期間が短すぎれば、パウチを剥がすとき粘着力が強すぎて皮膚にダメージを与え、反対に長すぎると便モレしやすくなってしまいます。
パウチ交換の目安を知るには?
パウチ交換の目安は、使用後のパウチの面板を観察することで知ることができます。
面板とは、ストーマ袋を固定する板のことです。
面板は、ストーマ袋を固定する以外にも、粘着剤と皮膚保護剤が使用されていているので粘着と皮膚を保護する機能があります。
この面板は、長く貼り過ぎると皮膚保護剤が溶けて崩れたり、白くふやけて内側から皮膚を守る機能が失われていきます。
パウチ交換のタイミングは、この面板の内側に浸食されて変化した部分、幅1cmくらいが目安です。
それ以上浸食されると、排泄物が付着して皮膚トラブルの原因になります。
外側からは判断できないので、パウチ交換の際に剥がした面板の裏側を見て、皮膚保護剤の溶け具合やふやけ具合を観察して評価することが大切です。
ストーマ保有者の親にご家族ができることは?
僕の考える、親が元気なうちからサポートできることは大きく2つあります。
1つは、ストーマ装具の手続きです。
永久ストーマになって最初にすべきことは、身体障害者手帳を取得してストーマ装具の給付制度の申請とその後の更新手続きです。
これらの手続きは、高齢者にとって分かりづらいこともあると思うのでご家族がサポートしてあげた方が良いでしょう。
2つ目は、状況の変化に応じて最適なパウチを見つけてあげることです。
ストーマ保有者が、できるだけ元通りの生活を送るには身体に合うパウチを見つけることに尽きます。
母が要介護になったとき、それまで使用していたパウチがかなり型の古いタイプで驚きました。
病院で合わせてもらったものと比較すると、見た目も重さも全く異なり明らかに扱いづらそうでした。
しかも、価格が安い訳ではなく、反対に少し高いくらい。
母は、55歳でストーマ保有者になってからは完全に引きこもり状態だったので、装具が進化していても情報を上手く取り込むことができずに取り残されてしまったのだと思います。
パウチが扱いやすくなれば、それだけ親の負担も軽減できるので、定期的にストーマ外来に連れて行くなどしてストーマ装具のメンテナンスをしてあげてください。
おわりに
僕のこれまでの経験から、ストーマ介助で役立ちそうな知識をまとめましたがいかがでしたか?
確かに、ストーマケアは下の世話だけにデリケートな問題です。
我が家のように話し合われることなく、ある日突然、家族にストーマ介助が移行されることも多々あるかと思います。
僕の後悔は、ストーマ介助の知識を入れておかなかったこともありますが、母の苦労を共有してあげられなかったこともあります。
母は、外出する際は絶食をして水分摂取さえも控えていたようでした。
今から思うと、排泄を抑えるためだったのでしょう。
水様便がたまると、ちゃぷちゃぷして動きづらいでしょうし、臭いやモレの恐怖もあったのだと思います。
母が、ストーマの管理に苦労していたことは、現在を見れば容易に想像できるので本当に悪いことをしたと思っています。