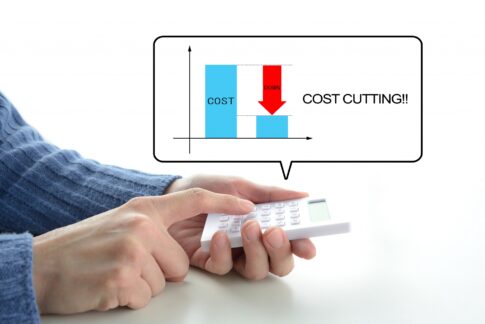母が、入退院を繰り返していた大学病院の退院通知は、突然でいつも慌てます。
他の病院は、退院前になると前もって
「もうそろそろ退院ですよ」
と教えてくれるのですが、どうも大学病院は相性が合わないと言うべきなのか・・
退院後の日常生活への復帰、不安や準備もあるので、突然の退院や転院を通告されるのは本当に困ります。
ただ、僕自身も、「なぜ、せき立てられるような退院をいつもしなければならないのか?」という疑問を持ちつつ、こうして記事を書くために調べるまで、その仕組みを知りませんでした。
僕のように病院側から突然、退院や転院を通告されて慌てられた経験をお持ちの方も多いと思います。今回は僕の体験を通して「なぜ、完治していないのに退院させられることになるのか?」を考えたいと思います。
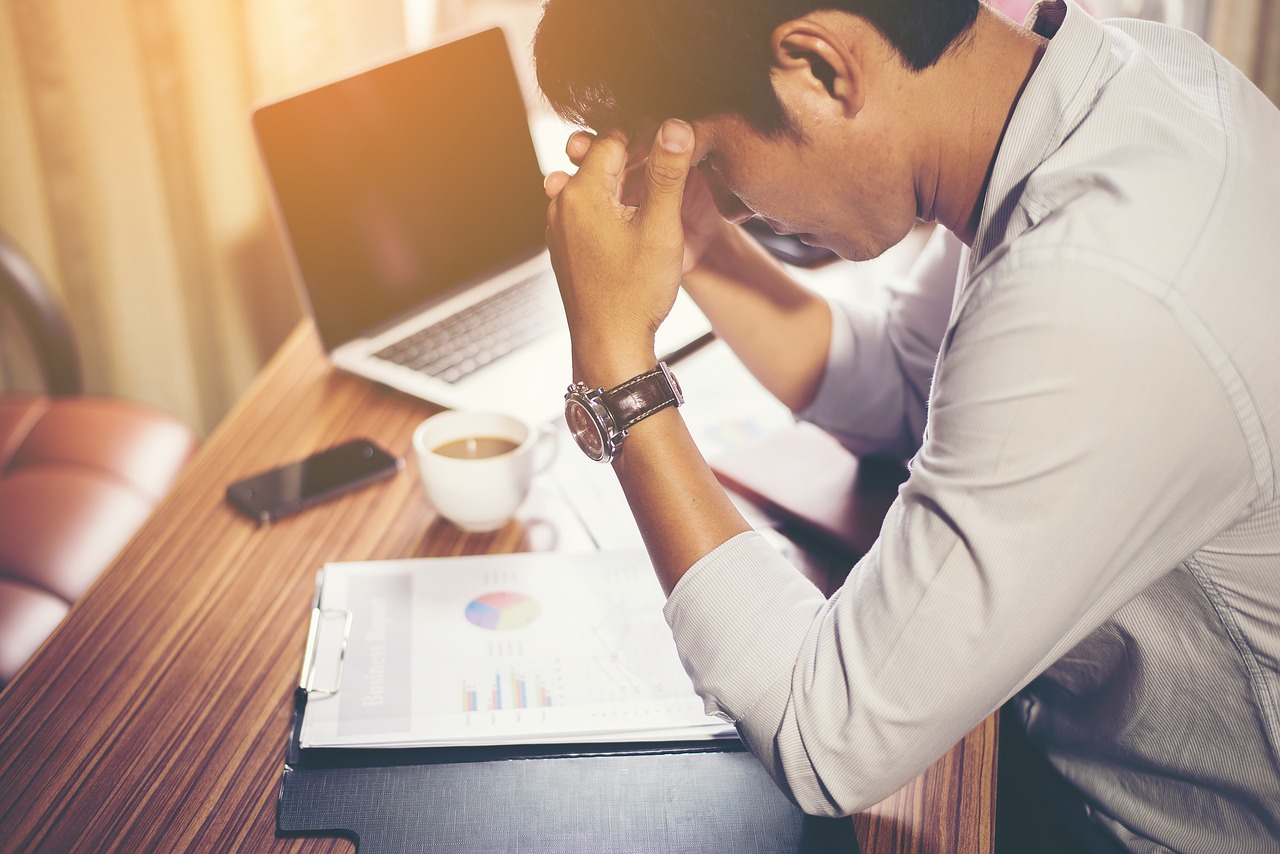
僕の長年の経験で、急に退院を通告される原因は想像するに2つあります。
- 単に、担当医の気配りが無い。
- 長期入院や、病状にそぐわない入院期間になったとき。
一つ目は、前もって退院までのおおよその流れを教えてくれれば、患者側も慌てなくて済むのですが、それが出来ない医師がいます。
ここは、急性期病院なので入院期間が短いことは、患者が知っていて当然とでも思っているのでしょうか?外見はどうか分かりませんが、相当な上から目線の医師も実際にはいます。
彼らの中では当たり前のことでも、説明が無ければ患者は分かりません。とにかく説明不足の一言です。
患者からすると、病気を治してくれるかどうかの評判を調べることはあっても、病院の看護体制のランクや急性期病院のことを知ったうえで、病院にかかる人は少ないと思います。
普通の方は「急性期病院って何のこと?」のはずです。
急性期病院とは、発症まもない患者のことで、一定期間集中的な治療をするための病床をもつ病院。入院期間は、一か月位を目途と設定している所が多く、早い方は一週間から二週間位で退院のケースもあります。
二つ目は、経営上の理由です。
厚生労働省が、診療報酬の点数設定で、急性期向けの病院とそうでない病院に分かれるよう、誘導しています。病院ごとの役割を明確にすると同時に、医療費のかかる入院期間を短くしたいという意図があります。
特に、急性期向けの病院は、在院日数が2~3週間を過ぎるあたりから、低い点数の入院基本料しか取れなくなると同時に、この1日あたりの入院基本料も、入院期間が長くなるにつれて下がっていきます。
これが、入院患者を追い立てる仕組みです。
患者のできるだけスムーズに退院や転院したい思いと、病院側の経営のためには、次の患者のためにベッドを空けないといけないせめぎ合いですので、無用なトラブルを避けるためには、なおさら病院側の説明は必要不可欠だと思います。
母が要介護になってしまった6年前に半年間、大学病院に入院した時もそうでした。
仕事中に、大学病院から携帯に「〇〇日に退院してください」と連絡が入り、4、5日後の週末に慌てて退院した苦々しい経験があります。
半年も入院したのに、退院するときはお世話になった看護師さんにもご挨拶できず、追い立てられて出ていく様は、夜逃げでもしているような気分でした。
毎週末には、必ず病院には行っていたのにもかかわらず、なぜ携帯にするのだろうと不思議に思ったものです。
半年も入院を余儀なくされたのは、僕が別に無茶を言って居座った訳ではありません。
原因が低ナトリウム血症だということに、たどりつかなかった医師だけに、入院中に二度も現在も継続している点滴の投与を止めた結果、何度も痙攣発作を引き起こしてしまい入院が長引いただけです。
おまけに後遺症まで残ってしまい、退院できるような状況ではありませんでした。
退院した時も、まだ母の状態は悪く見切りで退院させられたと思っています。
挙句、点滴の中身を間違って在宅医に引き継がれ、3日後には痙攣を引き起こしてしまい救急車で搬送、さらに一ヵ月の入院を余儀なくされてしまいました。
この時、とりあえず、在宅で点滴を継続してくれる病院だけは探しましたが、ケアマネも要介護認定も何も分からない状態での退院でしたので、何をどうすれば良いのか分からず、不安だけが募るばかりでした。
当時は、病院に対してマイナスのイメージだけが永遠に続いている状態でした。
今、当時を振り返っても、主治医に対して能力不足と不親切、それに悪意さえ感じています。
昨年8月中頃、この時は母が大腿骨を骨折、大学病院で手術して入院中でした。
退院後に向けてのことは、病院内のソーシャルワーカーの男性と一度会って転院先の話は伺っていました。
僕としては、この時はまだ母に、元通り歩行して欲しいと願っていましたので、リハビリのできる病院を希望していたのですが、リハビリテーション病院には内科や外科が基本ないので、母の病状では難しいようでした。
この頃になると大学病院の事も少しは分かっていましたので担当者に、
「まだ入院していても大丈夫ですか?」
「切羽詰まって慌てて判断したくないので入院期限があるようでしたら、前もって教えて下さい。」
と確認していましたが、その時は「入院期間なんてないですよ、大丈夫です。」と、にこやかに答えて下さっていました。
県内の施設名を数件書いたメモをもらったので、自宅に持ち帰り調べてみましたが、母の持病をケアーしながらとなると、どの施設も条件が合うところが無かったです。
一週間後に、ソーシャルワーカーから、リハビリできる施設はやはり厳しいと携帯に連絡が入りました。
療養を目的とする病院にも幅を広げさせて欲しいとの申し出がありましたので、その方向でお願いをすると同時に、隣接する大阪でリハビリ病院があればそちらの可能性も探って欲しいと付け加えておきました。
その翌日に、ソーシャルワーカーから携帯に連絡が入ったのですが、急展開な話と厳しい内容に驚きました。





今初めて聞いて知ったばかりの病院ですし大阪からわざわざ来ていただいて、もしお断りするようなことになっても申し訳ないので、明日の視察は一旦断っていただけませんか?



人が変わったかのような対応と、想像していなかった展開にびっくりです。
担当者の言葉遣いは丁寧でしたが押しつけムードが強く、安易に返事をしてしまうと押し切られそうでした。
僕としては、家族の知らないところで勝手に話を進められるのは気持ちが悪いですし、一時間はかかる距離を家族がいないのにわざわざ視察に来るというのも不審です。
向こうも商売、タダでは来ないはずです。
第一、勝手にレールをひかれる事が何よりも感じが悪いです。
そのレールの先には何があるのか・・?
嫌な予感しかしません。
担当者は、明らかに即決を僕に求めていました。
僕は仕事中で、思惑が分からず話も進みませんでしたので、リハビリのできる病院は諦め、現在かかりつけ医である中核病院に転院可能か確認をお願いして、可能であればそこに行きますと伝えました。
そして、視察の件はその場で丁重にきっぱりお断りしました。
もともと受け入れ先が難航した時には、母の状態を把握してくれている中核病院が安心だと思っていたので、運よく受け入れてもらい助かりました。
あくまでも僕の想像ですが、長年接してきたこの大学病院は相当風通しが悪いのだと思います。病院側にも事情があるのでしょうが、途中から手のひらを返したような対応には驚かされます。
いつも途中から急に流れが変ります。院内のプレッシャーなのでしょうか?
よく大病院の医療ドラマでありがちな天の声があるのか?それとも白い巨塔なのか?
ドラマの内容は、あながちフィクションでないのでは?
と思わずにいられません。
どのような組織でも可視化が進む現在、これでも病院の体質を改革しているのだと思いますが、それでもまだまだ閉ざされた世界という印象は拭えません。

身体に不安がある状態での退院や転院は決して珍しいことではないと言うことは、長年の経験で、今は理解できます。
先端医療や高度な医療提供を担う大学病院は、急性期の治療が終われば早々に転院か退院させることや、腰を据えて療養やリハビリもできないことも今は知っています。
通常、病状に関係なく入院させてくれる日数は、1回に付き最大3ヶ月が限度です。
そこには退院後は介護が必要になるだとか、身体の状態に心配が残る高齢者であっても例外はありません。
理由は、国が診療報酬制度でそうなるように仕組んでいるからです。
入院日数が長くなるほど診療報酬の費用が減り、病院経営が成り立たなくなります。その限度が3ヶ月です。
そう考えると、入院した時から退院時期はほぼ決まっていると考えて差し支えはないと思います。
現状の需要・供給、国の医療や介護保険の赤字など考えると、入院期間はこれから今以上に短くなっていくと考えるのが普通です。
まずはじっくりこの病院で病気を治してからなんて思っていたら、身の回りのことがままならないまま自宅に帰るしかなくなってしまったということにもなりかねません。
入院当初から、退院後の生活や介護についての心構えや準備をしておくことが大切になってきます。