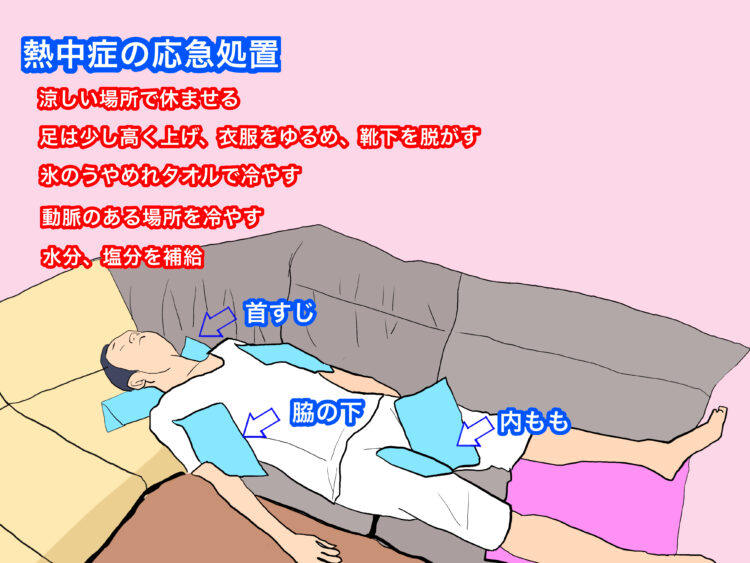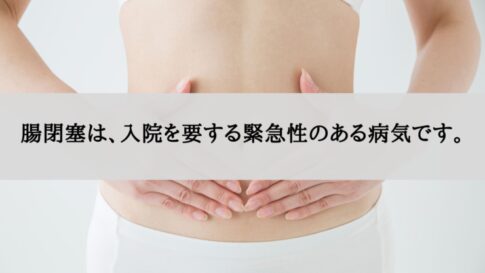親が入院すると、容態の心配や入院生活への不安から精神的負担が大きくのしかかってしまうものです。
また、介護度が高くなるほど入院準備や洗濯など、ご家族のフォローが必要になるので肉体的負担も強いられるでしょう。
今回の記事では、親の入院生活を省エネでサポートするポイントをまとめました。
親の入院生活をサポートするコツを知っていれば、少しはご家族の負担も軽減されると思いますので参考にしてみてください。
目次
最初が肝心!入院前の面談で不安や要望を伝える
 入院前に、担当看護師と患者やそのご家族であらかじめ書き込んだ患者情報用紙をもとに面談が行われます。
入院前に、担当看護師と患者やそのご家族であらかじめ書き込んだ患者情報用紙をもとに面談が行われます。
その目的は、患者の病状把握や服用している薬などの情報収取。
その他にも、日常生活動作に関することや心配事をすくいとって入院中の支援に反映させる意図もあります。
時間にして20分くらいですが、在宅でどのような生活していたかなど、ここでしっかり不安や要望を伝えておくことがポイントです。
我が家の場合だと、
食事については、腸閉塞(ちょうへいそく)の恐れや咀嚼(そしゃく)も弱っているので朝・夕はおかゆ。
褥瘡(じょくそう)になりやすいので、エアーマットレス希望。
1日3食、食後1~2時間、車いすに座らせて欲しいなど。
僕の心配は、環境の変化での寝たきりや認知症なので、できるだけ在宅生活に近づけてもらいたい気持ちがあります。
以前、伝え忘れで朝食にご飯が出されてしまい、なかなか変更されないことがありました。
入院中は、看護師も日々の業務が忙しいうえに交代でコロコロ変わるので何度も言わなければならなくなるハメになりがちです。
親に不自由な思いをさせないためにも、入院前の面談で伝え忘れのないように日頃からメモを取っておきましょう。
医療費が高額になりそうなとき!あらかじめ「限度額適用認定」の手続きを
医療費が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担ですよね。
そんなときは、加入している健康保険に申請して「限度額適用認定証」を事前にもらっておきましょう。
「限度額適用認定証」を利用することで窓口での支払いを自己負担上限額までにすることができます。
ちなみに上限払いの対象となるのは、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療です。
医療機関窓口で「限度額適用認定証」や保険証などを提示すると、1か月の支払いが自己負担限度額までとなり、超える分は支払わなくて済みます。
「限度額適用認定証」は、年齢・所得によって事前手続きが必要になります。
詳しくは、病院に制度についての質問や相談に乗ってくれる医療福祉課があると思いますので相談してみてください。
入院必需品リストをまとめておく
入院となると、着替えなど日常生活に必要な物を準備しなければなりません。
しかし、アレも、コレもじゃすぐに荷物が肥大化してしまいがちに(-_-;)
個室ならまだしも、大部屋だと置けるスペースも限られているので荷物を必要最小限に留める必要があります。
荷物をコンパクトにまとめるって、なかなか難しいんですよね。
また、忘れ物もありがちなことです。
予期しない入院ならなおさら、急に準備しなければならなくなると必要不可欠なものを忘れることもあると思います。
忘れ物を病院に持って行くのは、それだけで手間です。
そんなときのために、入院必需品リストをまとめておきましょう。
僕は、今でも過去の記事を忘備録代わりにして入院準備をしています。
会社勤めをしている方だと、災害バッグの感覚でキャリーバッグに入院必需品を備えておくとすぐに持ち運びできるので便利ですよ。
各種レンタルサービスを活用する
病院には、必需品レンタル業者が入っています。
「入院セット」などと呼ばれる、入院時に必要となる、衣類・タオル・日用品類をレンタルするサービスです。
仕事などで、入院中の親の身のまわりの世話をする時間がとれない方も、持ち込んだり洗濯しなくて済むので負担を軽減してくれます。
コスパで考えると、日額300円として20日間入院したとすると6.000円。
2ヶ月入院した場合は、18.000円。
単発の入院で6.000円であれば、買い揃えて洗濯する労力を考えればレンタルした方がお得です。
反対に、長期の入院や今後も入退院が予測される方は、その度にレンタルしていると相当な出費になるので状況に応じて使い分けた方が良さそうですね。
問題の解決を図るために、医療ソーシャルワーカーに相談をする
親の入院中は、医療費などの経済問題や転院に関すること、その他にも退院・社会復帰への不安など様々な問題が降りかかるものです。
経験したことのない事態に、ほとんどの人は立ち止まってしまうでしょう。
また、親をサポートしなければならない責任感から不安になる人もいると思います。
そんなときは、医療ソーシャルワーカーに相談してみてください。
医療ソーシャルワーカーとは、医療機関などにおける福祉の専門職で、病気になった患者や家族を社会福祉の立場から支援する職業の人です。
高齢化社会で、医療と福祉の連携強化が求められるこのご時世。
医療だけでなく、福祉にも力を入れなければならなくなってきているので、医療ソーシャルワーカーを備える病院も増えてきています。
病院によっては、「地域医療連携室」「医療福祉相談室」と名称が異なるようなのでご確認ください。
おわりに
僕の経験から、親が入院したときの負担を軽減するポイントをご紹介させていただきましたがいかがでしたか?
特に、寝たきりになるなど退院後の生活が変わる入院は、この先の不安から肉体面よりも精神面の方が消耗させられます。
経験者曰く、精神面のダメージは気づきにくく蓄積するので本当に厄介です(-_-;)
こんなときこそ、医療ソーシャルワーカーにご家族が抱える悩みや問題を相談されることをおすすめします。
医療ソーシャルワーカーは、福祉に関する公的支援制度や高齢者福祉施設や事業所の知識を持っているのできっと力になってくれるでしょう。
恥ずかしい感情から、相談することに抵抗がある方もおられるとは思いますが、助けて欲しいときに声を挙げることが一番大事です。
後々、恩を社会に返せば良いだけだと割り切って負担軽減に努めましょう。