在宅介護をされている皆さん!
親に、インフルエンザの予防接種を受けさせてあげていますか!?
恥ずかしながら僕は、訪問診療でインフルエンザの予防接種ができることを長らく知らなかったので受けさせていませんでした。
過去に、在宅医を一度だけ替えているのですが、最初の開業医は母が通院困難になっても予防接種の対応をしてくれなかったこともあります。
もし、かかりつけ医を替えていなければ、未だに知らずにいるかもしれませんね。
今回は、在宅でインフルエンザ予防接種を受けるための手続き・注意点をまとめておきますので参考にしてみてください。
目次
公費負担でインフルエンザ予防接種を受ける条件
 インフルエンザ予防接種はB類疾病のため、自らの意思で接種を希望する方が受ける予防接種です。
インフルエンザ予防接種はB類疾病のため、自らの意思で接種を希望する方が受ける予防接種です。
B類疾病とは、個人の発病・重症化防止目的で行うもので、自らの意志と責任で接種を希望する場合にのみ接種を行うものです。
対象者の意思確認ができない場合は、予防接種法に基づいた予防接種を行うことはできません。
対象者
対象者1
満65歳以上の人(接種当日)
各自で、市内の登録医療機関に予約をとってください。
65歳以上であることを証明するもの、健康保険証などを持参すれば大丈夫です。
対象者2
満60歳以上65歳未満の人、次のいずれかに該当する人
心臓、じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
接種費用
今年度に限り、上記対象者は無料で接種できます。(自己負担金はありません)
母の場合だと、例年1500円支払っている費用も今年は無料です。
接種回数
公費助成で接種を受けることができる回数は、1年度につき1回限りです。
2回目以降の接種は、全額自己負担になりますのでご注意ください。
実施期間
令和2年10月1日~
各自治体で、実施期間が異なるのでご確認ください。
※実施期間以外に接種された場合は、任意の予防接種となり全額自己負担となります。
接種前に手続きが必要な方
対象者2の人と、市外の医療機関で接種を受ける際は接種前に申請が必要です。
うちの84歳の父親は、通院できるので市内の医療機関に予約さえすれば無料で接種できるのですが、母親は市外の医療機関の訪問診療なので接種前に申請が必要になります。
手続きする場所は、各市町村の健康推進課です。
対象者2の方は、いずれかの書類の持参が必要となる自治体もあるので確認してください。( 医師の診断書 ・身体障害者手帳(1級)・病名が確認できる医師の証明書)
市外の医療機関で接種される場合も、障がいなどで自署できない人は、障害者手帳または健康保険証、本人印が必要です。
また、同一世帯の家族以外の人や代理の人が来る場合は、委任状(本人印)または、本人(接種を受ける人)の確認書類(コピー可)が必要となります。
インフルエンザの予防接種は、自治体によって実施期間や接種前の申請手続きに必要な物もまちまちです。必ずお住いの市町村のホームページで確認してください。
インフルエンザ予防接種は意外とリスクが大きいので確認を!
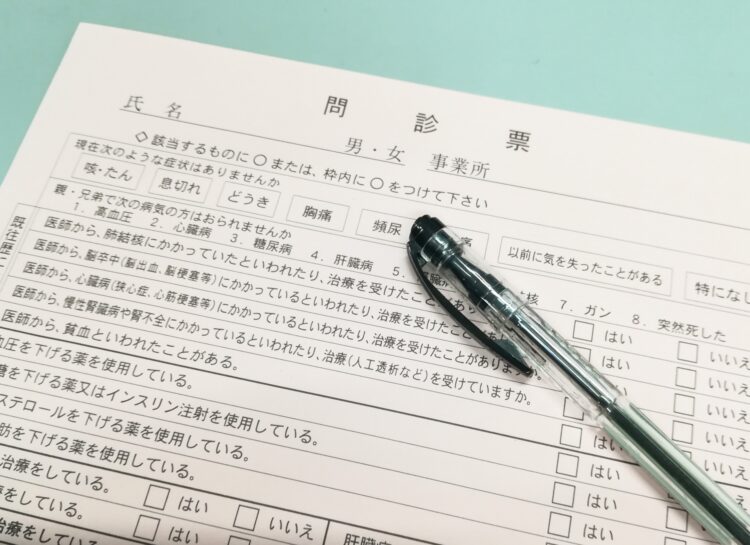 インフルエンザ予防接種は、高齢者の発病防止や特に重症化防止に有効であることが確認されている一方で、発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害などの副反応のリスクがあります。
インフルエンザ予防接種は、高齢者の発病防止や特に重症化防止に有効であることが確認されている一方で、発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害などの副反応のリスクがあります。
まれにショックやじんましん、呼吸困難などがあらわれることもあるようです。
インフルエンザの予防接種を受ける場合は、説明書をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解してからにしてください。
気になることや分からないことがあれば、予防接種を受ける前に在宅医に相談しましょう。
予診票は、接種をする医師にとって予防接種の可否を決める大切な情報になるので、代筆する場合はご家族が責任を持って正確な情報を記入してください。
予防接種を受けることができない人
- 明らかに発熱のある方。(体温が37.5℃を超えている場合)
- 重篤な急性疾患にかかっている人
急性の病気で薬を飲む必要のあるような人は、その後の病気の変化が分からなくなる可能性もあるので、その日は見合わせるのが原則です。
- 過去にインフルエンザワクチンの接種を受けて、アナフィラキシーを起こしたことがある人
「アナフィラキシー」とは通常接種後約30分以内に起こるアレルギー反応のことです。
発汗、顔が急にはれる、全身にひどいじんましんが出る、吐き気、嘔吐(おうと)、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き血圧が下がっていく激しい全身反応です。
- 過去にインフルエンザワクチンの接種を受けて、接種後2日以内に発熱、発疹(ほっしん)、じんましんなどアレルギーを思わす異常がみられた方
- その他、医師が接種不適当な状態と判断した場合
予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなくてはならない人
- 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人。
- 過去にけいれんの既往のある人。
- 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる人。
- 間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器疾患を有する人。
- インフルエンザ予防接種の成分、または鶏肉、その他卵製品などに対してアレルギーがあると言われたことがある人。
予防接種を受けた後の一般的注意事項
- 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- インフルエンザワクチンの副反応の多くは24時間以内に出現しますので、特にこの間は体調の変化に注意してください。
- 入浴は差支えありませんが、注射した部位を強くこすらないでください。
- 接種当日は、激しい運動や大量の飲酒は避けてください。
訪問診療でインフルエンザの予防接種を受けるメリット
母の「かかりつけ医」は市外なので、接種前に役所に行って申請しなければならない面倒はありますが、自宅で予防接種が受けられるメリットは大きいです。
その他にも
- ワクチンが不足している年でも、母の分を優先して確保してもらえる。
- 日頃、母の状態を把握していただいている在宅医にお願いできるので安心。
- コロナ鍋の中、病院に行くリスクを減らせる。
- 家族も一緒に予防接種ができる。
2年前から、母と一緒に僕も予防接種をしてもらっています。
費用は、今年は無料ですが例年は全額負担です。
おわりに
今年は、新型インフルエンザと季節性インフルエンザが同時に流行する可能性があると言われているだけに例年と少し勝手が違うようです。
厚生労働省も、令和2年度については過去5年で最大量の6300万人分のワクチン供給に備えているようで接種希望の方は早めにするように呼び掛けています。
高齢者のいる家庭では、ご家族が接種することで感染リスクを下げることにもつながるので、新型インフルエンザという不安要素がなくても予防接種をしておいた方が良いかと思います。








