昨年の7月に、母が大腿骨を骨折。
あれから早いもので、1年4ヵ月が経ちます。
当初は、治療すれば元通り歩けるようになると思っていたのですが・・・
「転倒・骨折」の知識が無かった僕は、事の重大さに気付けなかった残念な人です(-_-;)
幸い、認知症だけは逃れられましたが、こうして高齢者が寝たきりになるのだとつくづく思い知らされた出来事でした。
今回は、高齢者の大腿骨骨折について解説いたしますので参考にしてみてください。
目次
親がコケて痛みを訴えたとき救急車を呼ぶかどうかの判断は?

母の骨折は、台所の敷居をまたぐため、歩行器から手を離したときにバランスを崩して転倒したことによるものです。
しかし、転倒と言うよりは柱にもたれかかりながらズルズルと滑り落ちただけ。
そのときは、骨が折れていることも、まして2度と立てなくなることも知る由も無かったです。
なんせ、母を自家用車で病院に連れて行こうとしていたくらいですから・・・
親が、コケたとき救急車を呼ぶかどうかは迷うところです。
もし、「かかりつけ医」を持っておられたら、救急車を呼ぶ前に「かかりつけ医」に連絡した方が後々連携できるかもしれないので段取りが良いかと思います。
僕も、うずくまっている母を前に、どうすれば良いか分からなかったので在宅医がいる病院に連絡を取って指示をもらいました。
「かかりつけ医」が無い場合は、救急安心センター事業(♯7119)に電話してください!
「すぐに病院に行った方がよいか」や「救急車を呼ぶべきか」の回答をくれるはずです。
骨折するような転倒でなくても、高齢者は骨折している可能性があります。
無理に動かして、悪化させてしまう恐れもあるので、自己判断せずできるだけ専門家に判断してもらうようにしてください。
救急車で運ばれた病院で、無駄な時間を過ごさなければならないことも
救急搬送された病院は、一応内科はありましたが整形外科に特化した病院でした。
ここで、持病のある母を手術することができないと言われ、最初からつまずいています。
結局、医大に転院されるまでの10日のあいだ、この病院で待機を強いられることに・・・
しかも、その間、何の処置もされず、母はひたすら痛みに耐えなければなりませんでした。
高齢者の骨折は、いかにリハビリを早く行えるかがカギだと言うことは素人の僕でも知っています。
このもたつく状況に、どうすることもできない焦りとやるせない気持ちでいっぱいでした。
ちなみに、救急車で搬送されるとき、救急隊員には医大を搬送先に要望しましたが満床を理由に受け入れ拒否されています。
長年かかっていても、この病院は基本受け入れ拒否です。
術後、回復の兆しがないことに何かがおかしい
 「元通り歩けるかどうかは高齢なので分かりませんが、特に難しい手術ではなかったので手術自体は問題なかったです」
「元通り歩けるかどうかは高齢なので分かりませんが、特に難しい手術ではなかったので手術自体は問題なかったです」
術後に、手術をした医師からの言葉です。
手術は、右大腿骨の髄内(骨の中)にボルトを挿入し、スクリュー(ネジ)で固定するごく一般的な術式でした。
8月末に転院する際も「リハビリ頑張って下さい。」なんて言われて送り出されているので、リハビリさえできず寝たきりになるとは想像できなかったです。
9月に入ってもひどい痛みがおさまらず、転院先の医師は効く痛み止めを模索しています。
この時期、手立てのなさそうな病院の対応にとにかく苛立っていました。
まあ、転院先の病院からすると、リハビリで受け入れているのに話が違うと思っていたことでしょう。
転院先の病院で「骨粗しょう症」が重症化していることが判明
9月末、ようやく痛みの原因が分かってきます。
原因は、骨粗しょう症が重症化しているとの説明を受けました。
骨がスカスカで、大腿骨に入れたボルトを固定するはずのネジが抜け落ちそうになっているとのこと。
確かに、手術直後と現在のレントゲン画像を見比べれば一目瞭然です。
骨に差し込んだボルトを固定するために、垂直に入っていたネジの位置が全く違います。
ネジが、斜めになって本当に抜けそうでした。
このとき初めて、母はひどい骨粗しょう症だと言うことを知ることになります。
骨粗しょう症は、症状がなく気づきにくいため骨折してから分かるケースも多いようです。
しかし、母は闘病生活で16年にわたり医大に通院しているので訳が違います。
今頃、何言っているの?
内心、怒り心頭でしたが、転院先の整形外科の医師は週一度しか来ない非常勤医師。
ことのいきさつは関係ないので、さすがに何も言えなかったです。
術後の感染症は一番恐れていたこと
10月頃になると、在宅で入れている低ナトリウム血症対策の点滴に加え、高カロリー輸液、痛み止め、さらに抗生物質が追加されるようになり、一日中代わる代わる入っていました。
痛み止めは、なかなか痛みを抑えられず最終的には鎮痛効果で2番目に強い鎮痛剤を使っていると医師から聞いています。
抗生物質の投与は、高熱が出て血液検査で炎症反応が出ていたためです。
この時点で、一番恐れていた手術による感染症を引き起こしてしまいました。
高齢者は、手術で抵抗力が弱ることによって術後、感染症を引き起しやすくなります。
加えて、長期間の寝たきりで体力も低下の一途。
高齢者にありがちな、弱り目に祟り目です。
さらに厄介なことは、炎症反応は出ているのに原因がどこなのかはっきりしないこと。
菌が異物に付着する習性から、胸に入っているCVポートと手術で入れたボルトやネジもグレーゾーンです。
なので、CVポートは早々に除去されました。
しかし、足のボルトとネジは再手術不可と言われ取り除くことさえできなかったです。
抗生剤治療で菌を抑え込もうとしていたようですが、一向に高熱が収まらずご飯も食べられないほどに衰弱してしまい、この時期点滴だけで命をつないでいます。
骨折して入院しただけなのに認知症の心配
 11月頃になると、母の足の筋肉もすっかり削げ落ち、もう立ち上がれる感じではなかったです。
11月頃になると、母の足の筋肉もすっかり削げ落ち、もう立ち上がれる感じではなかったです。
表情もうつろで口数も少なく、このまま入院が長引くと認知症になるのでは?と不安を募らせていました。
9月頃はまだ医師に、

と言っていた僕も11月頃になると

足は諦めるので、認知症だけは勘弁してください
と変わっていました。
これ以上この状況が長引けば、たとえ骨折は治ったとしても寝たきりになるのは目に見えていましたし、認知症の恐れも出てきていたのでとにかく心配でした。
もう、リハビリどころではありません。
この時期、先が見通せない不安しかなかったです。
退院後の生活を考える!どこに目標を持ってくるかが大切
昨年の11月頃は、この状況を打開する何か良い方法がないかネットで大腿骨骨折についてよく調べていたものです。
しかし、「高齢者は、術後の死亡率が高い」だとか、やれ「リハビリ入院の実態の真実は、寝たきり製造入院」だとか、どうすれば歩けるようになるかを探しているのにネガティブな記事ばかり。
探せば探すほど、モチベーションが下がって行きます。
そして、これが現実なんだと改めて思い知らされました。
その記事の中に、「リハビリの最終ゴールをどこに持ってくるかが大切」との内容のものを読んで深く納得させられたのですが
「現実を受け止めて、これからどのような経過をたどるのが母にとって良いかを考えよう!」
そう考えたとき、認知症の回避その一点でした。
そのためには
できるだけ早く退院すること
それを妨げる高熱、ひどい痛みにメドを付けてもらうこと
退院後は、車椅子生活を目標にすること
医師に、このことを伝えました。
高熱は、尽力いただいて昨年の12月に収束。
痛みの方は、見切りでしたが自宅療養で様子を見ることに。
そして、退院前カンファレンスを経て、今年1月末に退院しています。
あれから1年経つ今も、2種類の痛め止めを服用していますが、最近ようやく母からの痛みの訴えも少なくなってきた感じです。
今思うとあの時、こうせざる得なかったのかもしれませんが、僕自身は現在の母の状態に納得しています。
おわりに
 結局、母は今年1月末に退院するまで半年以上ベッドの上で寝たきりでした。
結局、母は今年1月末に退院するまで半年以上ベッドの上で寝たきりでした。
母が、再び歩ける可能性があったかを考えると、骨粗しょう症が重症化していたので骨折してからでは何をしても結果は同じだったと思います。
しかし、入院から退院までの一連の流れをみたとき、これだけもたつくと歩ける人も歩けなくなってしまうでしょう。
高齢者が足を骨折しただけなのに、認知症や亡くなって思わぬ結果に陥った記事を見ていると、これだけかみ合わなくて段取り悪く物事が進むことも珍しくないと考えていた方が良さそうです。
母のケースはごく1例かもしれません。
しかし、あらかじめ知っていれば防げることもあるかと思います。
僕の、失敗の経験から言えること。
親が、元気なうちから骨粗しょう症の検査と、「かかりつけ医」があれば骨折したときの対処も想定して相談しておくことをおすすめします。
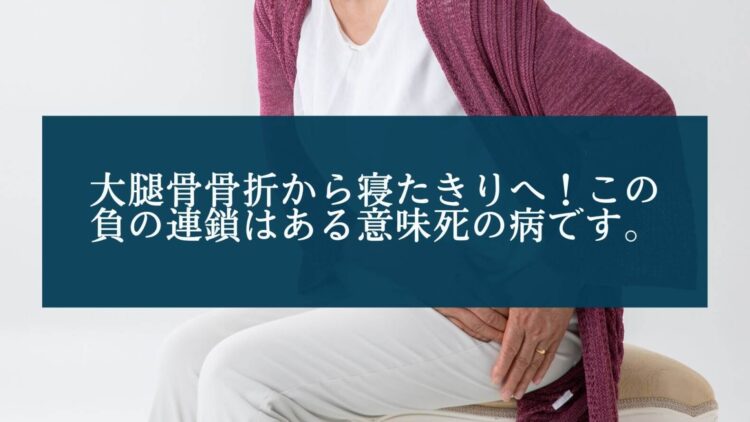






何とか歩けるようにしてください