「退院前カンファレンス」
聞き慣れない言葉です。
現在、母がかかりつけにしている病院で退院前カンファレンスを2度行ってもらっているのですが、
「一体、どんなことをするのだろう?」
最初はそう思いながらでしたので、何の準備もしていませんでした。
退院に向けて、何か準備をしなければならないとは思っていても、僕のように何をどうして良いか分からないまま退院前カンファレンスの日を迎えておられる方もおられると思います。
今回は、退院前カンファレンスとはどのようなことをするのか、その様子や目的をまとめましたので参考にしてみてください。
目次
在宅介護をするには、退院後の生活を想定してそれなりの備えが必要です!
 仮に、母のように歩行していた人が寝たきりになると、日常生活の介助もこれまでとガラリと変わってしまいます。
仮に、母のように歩行していた人が寝たきりになると、日常生活の介助もこれまでとガラリと変わってしまいます。
しかし、経験していない人にとって退院後の生活はイメージしにくいものです。
「退院してから、何かと大変なんだろうな!?」
「まぁ、何とかなるだろう!」
当時の僕の心境ですが、今思うと考えが甘すぎます。
実際に、寝たきりの母を介助してみて分かることですが、何の対策もせずに自宅に戻って何とかなるレベルの話ではありません。
しかも、1年前の母の状況は大腿骨を骨折して手術するも、骨がつかずに痛みも治まらない寝たきりの状態です。
おまけに、僕の方というと仕事はギブアップ、体調も最悪!
しかし、重なるときは重なるものですね(笑)
「半年以上寝たきりの母を、自宅に連れ帰って果たして介護ができるの!?」
楽観的な僕でも、いろんなことを考えだすと夜も眠れなかったです。
そんなある日、退院前カンファレンスがありました。
退院前カンファレンスとは?
「退院前カンファレンスを、行いたいので予定をしておいてください。」
最初、看護師さんから連絡があったとき、「どんなことをするのだろう?」と思ったものです。
指定された日時に病院に行くと、いつも母を支えてくださる皆さんが勢ぞろいしているではありませんか!?
主治医や看護師など病院側の人に加え、ケアマネ、訪問看護師、訪問リハビリ、介護レンタルの人まで総勢9名。
病院側と在宅での生活をサポートしてくださるスタッフとのあいだで、病状や状況についての引継ぎや今後の打ち合わせを行うために一堂に会する必要があるのですが、何が始まるのかと少し驚いたのを覚えています。
ちなみに、退院前カンファレンスを主催するのは、入院している医療機関の医療ソーシャルワーカー、もしくは院内看護師です。
医療ソーシャルワーカーがケアマネに連絡して、カンファレンスの日程調整をします。
退院前カンファレンスは、退院後、在宅で安心・安全な療養生活ができるよう、病院から在宅へ速やかに引き継げるように支援することを目的にしています。
なので、ここで話し合われることは在宅介護を行うために必要なことすべてです。
これから、在宅介護を始めなければならない方なら、
「介助が必要になった親が、自宅に戻って生活をするためには何が必要になるのか!?」
「そのためには、どのような介護サービスを手配しなければならないのか!?」
このようなテーマで、患者の状態を鑑みて退院後の生活を予測しながら必要な介護サービスが話し合われます。
また、我が家のように在宅介護中の入院でも同じです。
特に、入院前よりも介護度が重くなった場合は、在宅介護に復帰・継続するために何が必要になるのかが主な議題になり退院後の生活に反映されていくので、今後の生活を左右する重要な場になります。
今年1月の「退院前カンファレンス」の内容
病院の医療ソーシャルワーカー(院内スタッフ)進行のもと、皆さん簡単な自己紹介から始まりました。
主治医から病状説明
まず、主治医から速やかに在宅復帰をするために!と前置きがあったうえで、入院の原因となった右足大腿骨骨折についての現在の病状、入院前と異なる点、今後の治療計画と心配される予後の説明がありました。
内容としては、上記のような感じでした。
それぞれ異なる職業の人が集まったディスカッションの内容
この場では、生活するうえで必須となる条件が話し合われました。
- 排泄介助
- 点滴の管理
- 緊急時の体制
- 入浴
- 移動手段
「退院後の食事や下の世話は、誰がするのですか!?」
まず、最初に病院看護師から質問がありました。
集まっていただいた人の中には、今回は自宅には戻らず施設に入ると思っておられた方もいたと思います。
ここで初めて、介護離職をして僕が母の世話をすることを伝えたのですが、やはり皆さん驚いていました。
さて、ここから自宅に戻ってからの生活について話し合われます。
担当医の説明を元に、それぞれの職業の立場から質問や意見が出されました。
病院看護師からは、自宅に戻ってからの食事の介助やおむつ交換に不安がないのか、また必要ないという僕に訪問入浴の必要性の話をされています。
在宅で点滴をしなければならない訪問看護師は、点滴の種類や手順は入院前と同じかどうかや据替されたCVポートの位置を担当医に確認。また、かかりつけ医が替わることによって、緊急時の対応も大幅に変更されましたので訪問看護師とその打ち合わせも行っています。
リハビリは、病院と訪問の理学療法士2名が来られていたのですが、引継ぎと自宅で必要となる車いすをレンタル業者と選定していただいていました。
難題だったのは、整形外科へ通院するための交通手段。
整形外科は、訪問診療が無いので通院するしかなかったのですが、夜診の18時からの診察しかなくこの時間帯に営業している介護タクシーが無かったからです。
行きは良くても、帰りがどうしても20時は過ぎるので引っ掛かってしまいます。
それに、ストレッチャーを持っている業者が少ないこともありました。
ケアマネが、心当たりのある業者を3件電話してくれていましたが解決できず、この問題だけは持ち越しています。
カンファレンスから退院日までは介助の仕方などを習得する準備期間
退院前カンファレンスは、退院後の生活に道筋をつけるための話し合いの場です。
ここで、退院までにどんな準備や対策をすれば良いのか課題も明確になります。
僕の場合、おむつ交換、車いすの扱い、それに車いすへの移乗も初心者でしたので、カンファレンスから退院までの短い間にすることは多かったですが、病院に行ったときは看護師に見てもらいながらできるだけ自分で介助するようにしていました。
その他にも、フォルティオという骨粗しょう症対策の皮下注射の打ち方もレクチャーしてもらい実践もさせてもらっています。
あと、ストーマ装具の便漏れがひどく看護師が困り果てていた状態での帰宅でしたので、当面のあいだ便漏れに悩まされるのは目に見えていました。
この問題も、入院中にメドをつけておかなければならなかったので、相談してストーマ外来に予約を入れてもらい退院までに何度か受診しています。
退院前カンファレンスで、退院日の調整が行われることも多いです。
もし、介助などの不安があるようなら、相談すれば多少退院日を伸ばしてもらうことも可能だと思います。
退院前カンファレンスは不安を軽減できる場でもある
親の介護で、気を付けなければならないことは一人で抱え込んでしまいがちになること。
不安や問題を抱え込んでも何の解決にもなりませんし、自力ではどうにもならない以上、それ以外のやり方で出来るだけの改善に取り組まなければ母と共倒れになるという危機感はありました。
退院前カンファレンスは、集まってくださった皆さんに不安や希望を聞いてもらうちょうど良い機会です。
これだけの人が集まって話せる機会は、早々無いと思います。
それぞれの専門分野がいるので、話してみれば案外簡単に解消できる問題もあるかもしれません。
それに、退院後の課題も見えてくるので不安の軽減にもつながるかと思います。
おわりに
 今回の、退院前カンファレンスの所要時間は1時間くらいでしたが、1人でないと実感できましたし、何かあれば訪問看護師やケアマネに相談すれば何とかなると思える良い機会でした。
今回の、退院前カンファレンスの所要時間は1時間くらいでしたが、1人でないと実感できましたし、何かあれば訪問看護師やケアマネに相談すれば何とかなると思える良い機会でした。
在宅介護を支えてくださっている方々は、チームみたいなものです。
強いチームのサポートは、安心して暮らせる生活に直結すると退院前カンファレンスを通じて強く感じました。
母を支えていただいている皆さんの様子を見て、時間はかかりましたが素敵な方々にめぐりあえたと感謝しています。



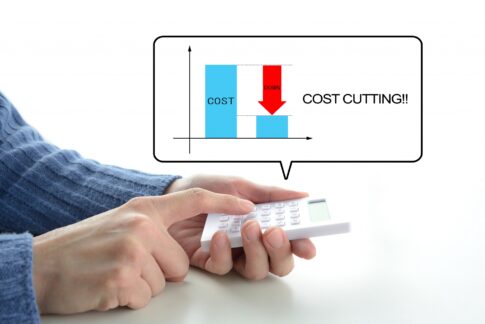


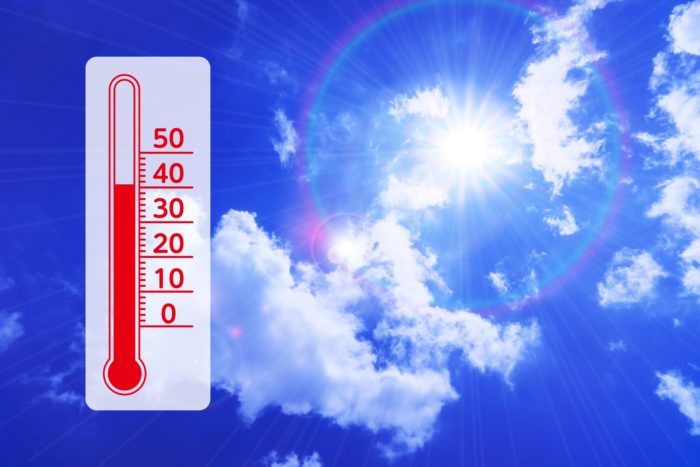



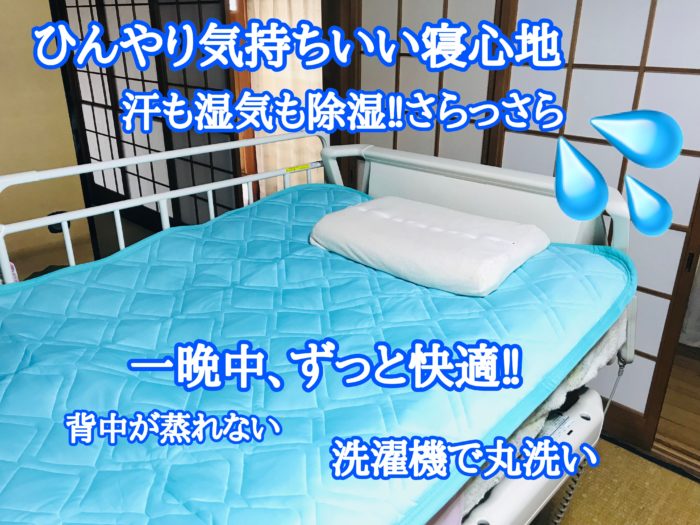




1.手術後の経過が芳しくなく、ひどい痛みが続いて半年のあいだほぼ寝たきりの状態
2.骨粗しょうの影響で骨がスカスカのため、手術して入れたボルトを固定しているピンが抜けかけている。退院後も足に負荷がかけられないので気を付けること。
3.入院中にポート感染をおこし、CVポートの位置が右から左胸の上部に場所が替わっている。
4.月一回の大学病院への通院が不可能になったため、かかりつけ医を大学病院からこちらの病院にシフトする。
5.今後の治療は訪問診療の医師が主治医となって引き継ぎ、骨折に関してはこちらの整形外科に通院する。