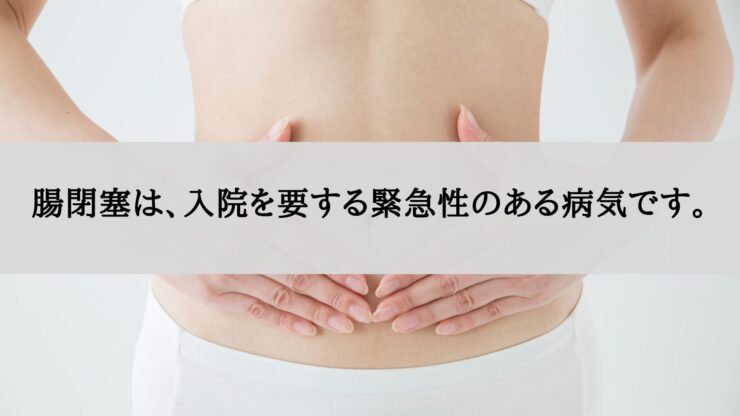腸閉塞との付き合いも、21年目になります。
困っているのが、繰り返し起こる常習性。
年4回なった年もあるので、入院回数はすでに30を超えていると思います。
会社から帰宅すると、母がうずくまって苦しんでいたことも。
食前まで予兆がないのも厄介です。
こんな調子ですから、食後は常に警戒していましたし、仕事中も自宅で倒れていないかいつも気がかりでした。
今回は、同じような悩みをお持ちの方に、これまで経験したことや得た知識をまとめましたので参考にしてみてください。
目次
腸閉塞は食べたものがお腹で詰まる緊急性の高い病気です。
僕が、よく参考にしているMSDマニュアル家庭版では腸閉塞のことが下記のように記されています。
腸閉塞とは、腸管内で食べもの、水分、消化分泌液、ガスの通過が完全に止められているか、深刻な通過障害が起きている状態のことです。(参照:MSDマニュアル家庭版)
母がなるのは、最も多いとされている腹部手術によって起こる癒着性腸閉塞です。
癒着性腸閉塞とは、癒着が原因で腸が捻じれ、細くなって通過障害をきたす状態を言います。
癒着とは、腸と腹腔壁や腸同士がくっつくのがもとで、腸管が曲がったりふさがったりすること。
母も、大腸がんで手術をしているのでその後遺症みたいなものだと認識しています。
しかしながら、食べたものがお腹の中で詰まりやすくなるなんて考えただけでもゾッとします。
対処が遅れるとどうなる?
治療が遅れると、開腹手術で詰まっている部分の腸管を切除しなければならなくなるケースも珍しくないようです。
また、腸閉塞を放置すると、食べもの、水分、消化分泌液、ガスが詰まって腸が膨張して破裂することも。
さらに症状がすすむと、腸内細菌が血管内に入って全身に回り、敗血症になって死に至ることもあります。
このように腸閉塞は、重症化しやすいので速やかに病院につなげることが大切です。
余談ですが
母は直腸、大腸のすべてを切除。
小腸も切除して、半分程度しか残っていません。
それなのに、残っている小腸で詰まりやすくなるとは・・・
縫合不全が原因で、術後の翌日に再手術をしてさらに小腸を切除した出来事はグレーゾーン。
少なからず、腸閉塞にも影響していると思います。
手術した医師の腕が悪いのか?
それとも運が悪かっただけなのか?
これだけ長いあいだ大変な思いをさせられているだけに、恨みごとの一つも言いたくなります。
腸閉塞の初期症状と病院に行くタイミングは?
 病院に行くタイミングは、初期症状を見極めて早めに病院に行くことに尽きます。
病院に行くタイミングは、初期症状を見極めて早めに病院に行くことに尽きます。
しかし、これがなかなか難しい。
病院だとCT検査で容易く分かることでも、ご家庭だと症状で見分けなければならないからです。
通常、腸閉塞の初期症状は、ガス(おなら)が出ない、気分が悪い、吐き気がある、便秘が長引いている、腹部全体が張ってチクチク痛むなど。
短腸症候群で人工肛門の母も、お腹の張り、汗ばみ、腹痛、吐き気、おう吐の症状が出ます。
ただ、腸が短いためか、他の人よりも進行が早いよう。
食べたものが20~30分で水様便として排出されるので、すぐに便が出なければ腸閉塞の疑いアリです。
この時点で、腸閉塞になる確率は高く40~50%というところでしょうか。
腸閉塞の症状が進むと動けなくなることも
母が、要介護になる前のことですが、判断が遅れて辛い思いをさせたことがあります。
断続的なおう吐が始まり、病院に連れて行きたくても動けなくなってしまいました。
そのうちに、おう吐の色が真っ黒い液体に。
腸から逆流してきたと思い、洗面器を持たせて慌てて病院に車を走らせています。
この経験から、母を病院に連れて行くタイミングは、腹痛、吐き気まで。
時間にして、食後5時間までと決めています。
その間は、電気カイロを下腹部にあてがって温めたりと、腸の働きを促して便が出るのをひたすら待ちます。
それでダメなら、病院に連絡して連れていく運び。
これで80%以上の確率でアウトです。
このように腸閉塞の症状が進むと、腹痛や嘔吐で動けなくなる可能性があるので早めに判断をするようにしましょう。
因みに、おう吐は小腸閉塞の特徴で大腸閉塞ではあまりみられないようです。
治療方法は?入院期間は?
幸い、母はこれまで腸管の閉鎖のみです。
これだけなら、点滴と絶食の保存的治療で治ります。
まず、入院して処置されることは、お腹で詰まっている食物を取り除くこと。
鼻から入れた胃管やイレウス管 (胃や小腸まで届く長いチューブ)で減圧して、腸に詰まった食物や廃液を吸い出します。
腸閉塞になると、腸液が大量に排出されるため脱水症状と電解質のバランスが崩れます。
点滴は、これら不足した水分やナトリウムなどを補うためです。
絶食することで腸を休め、点滴で水分と栄養補給をして回復させます。
入院期間について
通常、腸閉塞の入院期間は1~2週間くらいです。
入院して2~3日は、お腹で詰まっている食物を取り除くことに費やされます。
腸が正常に動きだしたら、食事を再開。
流動食→重湯→三分食→5分食→全粥→と普通食に段階を経て戻していきます。
通常の食事が、食べられるようになったら退院です。
しかし、母は3~4週間かかります。
元々、30kgそこそこしかない体にさらなる体重減。
加えて、体力の低下も著しいので退院できる状態まで回復を待たなければならないからです。
腸閉塞予防のために気を付けることは?
しかし、日常生活の中でいくつか注意すれば確率を下げることは可能です。
食事対策
食事対策で、気を付けたいことは2つ。
1つは、NGと言われている食べ物を避けること。
基本的には、消化の悪いものや脂っこいものは避けた方が良いでしょう。
特に、敬遠しなければならないのは食物繊維の多い食材。
具体的には、ごぼうやなどの根菜類、しいたけなどのキノコ類、昆布などの海藻類も食物繊維が多いです。
その他にも、こんにゃく、たけのこ、豆類、貝類、天ぷらなど消化の良くないものも控えた方が良さそう。
2つ目は、よくかんでゆっくり食べて腸の負担を軽減すること。
また、親が噛む力が弱くなっているようなら砕いて食べさせてあげる配慮も必要です。
お腹を冷やさない
母が、腸閉塞になるのは冬に集中しています。
おそらく寒さで、腸の働きが鈍るからだと思います。
腸の働きを良くするには、お腹を冷やさないこと。
それでなくても、冬場は食事以外で水分をとらなくなるうえに、寒さで運動しなくなるので腸の働きが鈍る季節です。
対策するには、温かい飲み物や食べ物を食することを心がけるだけでも良いと思います。
また、腹巻や湯たんぽで腹部を温めるのも効果があるでしょう。
母も、普段から薄着は避けて腹巻を付けていたものです。
腸閉塞を繰り返すようなら「かかりつけ医」を持つべき
母が、腸閉塞になるのは決まって夕食後。
常に、夜間に対応しなければなりません。
病院に連れて行って、腸閉塞と診断されると一旦帰宅。
入院準備をして、さらに一往復。
夜中に、車で片道30分の道中を行ったり来たり。
自宅に戻って一息つく頃には、夜が明けていることも。
ほぼ、徹夜です。
会社勤めをしていた頃は、疲れた体にムチ打ってもうひと仕事している感じで本当に辛かったです。
繰り返し起こる腸閉塞は、本人も辛いと思いますがサポートするご家族も相当な負担を強いられます。
負担を軽減するためには、腸閉塞に理解がある病院を見つけることが重要なポイントです。
自宅近くで、「かかりつけ医」を作っておくだけでもかなり楽になると思います。
幸い、腸閉塞の保存的治療は難しい処置ではありません。
「かかりつけ医」については、こちらの記事に記載していますのでチェックしてみてください。
緊急時の受け入れに消極的なら「かかりつけ医」を変えることも検討しよう
緊急時の受け入れに消極的な医大を、「かかりつけ医」にしていた僕の反省から。
特に、医大は夜間の対応が悪かったですね。
夜遅くなので仕方ないのかもしれませんが、電話の取次に10分以上待たせるのもザラです。
挙句、満床を理由に受け入れてくれなかったり、
翌朝の診察時間まで待てないのかと言われたことも・・・
腸閉塞かもしれないのに、全く話になりません。
とにかく、入院の度に違う病院にふられて消耗させられました。
この問題を解消したのは、皮肉にも介護離職してから。
母が、大腿骨骨折して医大に通院不可となり、在宅医のいる病院にシフトしてからです。
正直、長年かかっていた医大から離れることは不安しかなかったですが、思わぬことに緊急時の対処が円滑にいくようになりました。
現在は、訪問看護師に連絡するだけですべて行ってくれます。
腸閉塞かどうかの判断から、入院の受け入れまですべてです。
また、在宅時の点滴のことや処方薬など入院前の引継ぎもスムーズにいくようになりましたし、何よりも信頼している在宅医がいる病院なので入院中も安心です。
医大に苦言を言うなら
長年、母は月1回定期健診に通院していたので、医大を「かかりつけ医」だと僕は思っていました。
なので、緊急時も医大にすがるしか手立てがなかったのです。
しかし、これらの問題は「中核病院」や「かかりつけ医」の役割について知らなかったが故に生じていたもの。
今となっては、患者に中核病院の役割を伝えて、腸閉塞のフォローしてくれる病院を紹介するだけで済む話です。
患者側からすると、そんなこと教えてくれないと分からない!
医大にかかっていた19年間は、何やったん!?
と言いたくもなります。
もし、緊急時の受け入れに不安がある場合は、「かかりつけ医」を変えることも視野に探すことをおすすめします。
従来かかっている病院に、腸閉塞をフォローしてくれる病院の紹介を依頼してみても良いでしょう。
腸閉塞は救急車を呼んでもいいの?
病院ですぐ対応してもらえるようにあらかじめ連絡して、できればご家族に付き添ってもらうようにしてください。
我が家も、母が大腿骨を骨折してほぼ寝たきりになるまで、僕が病院に連れて行っていました。
ただ、腸閉塞はおかしいと感じた時にはすでにひどい腹痛やおう吐を引き起こしてしまう可能性があります。
不測の事態を回避するためにも、公共の交通機関や患者ご自身での車の運転は控えた方が良いでしょう。
腸閉塞は、すぐに命にかかわる病気ではありませんが入院を要する緊急性のある病気です。
ちょっと危ないと思えば、無理をせずに救急車呼ぶことをおすすめします。
救急車を呼んだ方がいいか、判断に迷ったときには救急安心センター事業(♯7119)を活用してみてください。
おわりに
今回は、繰り返し起こる腸閉塞の対策について解説しましたがいかがでしたか?
最後に、1つ注意して欲しいこと。
母は、腸閉塞を恐れるあまり食が細くなってしまいました。
そもそも、短腸症候群の影響で食べたものが吸収しづらいからだ。
それなのに、食が細くなったら本末転倒です。
あれもダメ、これもダメ・・・
腸閉塞の恐れがある食べ物や行為を言い出せば、きりがありません。
確かに、予防を意識した食事を徹底すれば効果は出るでしょう。
しかし、これじゃ息が詰まります。
それに、我慢をすれば必ず反動がくるので長続きもしません。
結局のところ、腸閉塞になるかならないかは運次第と割り切ることも大切かと。
好きなものを我慢せずに、細かく刻んだり軟らかく煮たりして調理の工夫をして食べる方が良いと思います。
できるだけ、胃腸を気遣う生活を心がければ腸閉塞になるリスクは減らせるはずです。