先日、母が入院したことのあるとある病院で、VRE院内感染があったと大きなニュースになっていました。
院内感染はよく耳にしますが、そもそもVREが何のことか分からない僕は知っている病院でなければ聞き流していたと思います。
ただ、病院だけでなく介護施設や在宅でも感染症になる可能性があるので、感染症のリスクを知っておいた方が良さそうです。
そこで今回は、高齢者のかかりやすい感染症を調べましたので良かったら参考にしてみてください。
目次
バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)について
この記事を書くきっかけになったバンコマイシン耐性腸球菌(VRE)。
騒ぎになるだけあって、現段階で効く抗生物質がないようです。
少し脱線しますが、やはり気になるのでバンコマイシン耐性腸球菌(VRE)について調べました。
バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)は人が作り出してしまった細菌
厚生労働省のHPでは、バンコマイシン耐性腸球菌感染症のことを、
「バンコマイシンに対して耐性を示す腸球菌(VRE)による感染症である。」
と一文で説明してあります。
しかし、これでは何のことか分かりませんよね。
この聞き慣れない感染症名の、名前の由来を知ると分かりやすいです。
1960年に作られた抗生物質メチシリンに対して、チシリン耐性⻩色ブドウ球菌(MRSA)が出現し、そのMRSAの治療のために開発された特効薬が「バンコマイシン」。
さらにこの抗菌薬「バンコマイシン」に対して、剤耐性を持った腸球菌が出現してしまったのがバンコマイシン耐性腸球菌(VRE)。
腸球菌は通常、健康な人の腸に存在していて、うんちの成分の1割以上は生きている腸内細菌とその死がいだそうです。
因みに、7~8割は水分で食物の残骸は意外に少なくて驚きました。
問題は、腸球菌が有効な抗生物質が少ない菌だということ。
ときに腸球菌は、感染症を引き起こす原因になってしまうことです。
バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)とは、本来効くはずのバンコマイシンという抗生物質が効かなくなった腸球菌のことです。
VREの起源は諸説あるようですが、一説には大昔から自然界の細菌が持っていた抗生物質に抵抗するための遺伝子が、なんらかの過程でヒトの腸球菌に入りこんだ、と言われています。
結局のところ、人類と細菌のせめぎ合いの末に生まれてしまった産物という訳ですね。
バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)の特徴
VREに感染しやすい人は、術後患者や感染防御機能の低下した高齢者です。
- 腹膜炎、術創感染症、肺炎、敗血症などの重症の感染症を引き起こし死に至る可能性が高まる。
感染経路
- VREは接触感染。保菌者の便から排出されたVREが、保菌者や医療従事者の手指からヒトへ直接感染、またはトイレ、ドアノブ、ベッド柵等の環境を介して広がる間接感染。
特徴
- 病原性が弱い細菌なので、健康な人は感染症を起こすことはない。
- 仮に、腸管内に感染または定着しても下痢や腹痛などの症状を呈することはなく無症状なので感染していても自覚していない人がほとんど。
- VRE はいったん保菌すると消えるまで長期間(数ヶ月)かかるため、長期にわたり腸内にとどまって感染源になる可能性がある。そのため、誰からいつ感染したのかなどを特定することが困難。
今のところ、VRE は病原性が弱い細菌ということがせめてもの救いです。
素人考えですが、高齢者はたくさん薬を飲むので、今後、剤耐性を持った菌が培養されてバージョンアップしていくのでは!?と思うとちょっと怖いですね。
主な感染経路と原因微生物
感染症とは、色々な病原体 (細菌、ウイルス、カビなど) が体の中に侵入して増え、咳や発熱、下痢などの症状がでることです。
身近なところでは風邪も感染症の一種で、ウイルスによって鼻水、発熱、だるさなどの症状を引き起こしてしまいます。
各感染症によって体の中に侵入するルートも異なるので、感染経路についても知っておいた方が良いと思います。
|
感染経路 |
特徴 |
主な原因微生物 |
|
接触感染 (経口感染含む) |
●手指・食品・器具を介して伝播する 頻度の高い伝播経路である。 |
ノロウイルス※ 腸管出血性大腸菌 メチシリン耐性黄色ブドウ 球菌(MRSA) 等 |
|
飛沫感染 |
⚫ 咳、くしゃみ、会話等で、飛沫粒子 (5μm 以上)により伝播する。 ⚫ 1m 以内に床に落下し、空中を浮遊 し続けることはない。 |
インフルエンザウイルス※ ムンプスウイルス 風しんウイルス 等 |
|
空気感染 |
⚫ 咳、くしゃみ等で飛沫核 (5μm 未満)として伝播し、 空中に浮遊し、空気の流れにより 飛散する。 |
結核菌 麻しんウイルス 水痘ウイルス 等 |
|
血液媒介感染 |
⚫ 病原体に汚染された血液や体液、 分泌物が、針刺し等により体内に 入ることにより感染する。 |
B 型肝炎ウイルス C 型肝炎ウイルス 等 |
出典:厚生労働省 高齢者介護施設における感染対策マニュアル
※インフルエンザウイルスは、接触感染により感染する場合がある
※ノロウイルス、インフルエンザウイルスは、空気感染の可能性が報告されている
感染症の恐ろしい特徴の1つは、原因となる病原菌がこれらの感染経路で人から人へ感染が広がっていくことです。
咳やくしゃみや触る行為もダメ。
空気感染に至っては、同じ空間にいるだけで感染してしまうのですから気を付けていても完全な予防は難しいと言えます。
高齢者がかかりやすい感染症
厚生労働省が、注意喚起している高齢者がかかりやすい感染症は上記表の赤字で記したものを含めざっとこんな感じです。
上から5番目の腸管出血性大腸菌(O157)まではよく耳にしますが、その他はご存知ない方も多いと思います。
僕も、今回調べて初めて知りました。
個々の感染症の症状については、厚生労働省の医学情報リンクを貼っておきますのでご確認下さい。
病院や介護施設の感染症のリスク
病院は、抵抗力が弱い患者が集団生活している密閉空間です。
病原性の高くないような菌でも持ち込まれてしまうと、たちまち院内感染の原因になってしまうことは予想できます。
感染ルートも医師や看護師、その他にも病院で働くスタッフやお見舞いに訪れる来院者もいるので、日々感染対策をしていても防ぐことはなかなか難しいのではないでしょうか。
介護施設も同じです。
入居者・面会に来られた家族・スタッフ・業者など、ホームに出入りする全てに気を配っているとは思います。
それでも、インフルエンザやノロウィルスといった感染症で入居者が亡くなるニュースが後を絶ちません。
介護施設の中には、感染経路を遮断するために外泊・外出を自粛したり、感染症がある人はそれを完治するまで入居できないことがあるのはそのためです。
在宅介護での感染症の可能性
過去に、訪問入浴のスタッフの1人がインフルエンザにかかって人手が足りなくなったので休ませて欲しいと言われたことがあるのですが、もし予防接種を受けていなかったのだとすると、「在宅ケアに従事している職業なのに認識低いのでは!?」と言いたくもなります。
在宅介護での感染ルートは、介護者や訪問看護師などの在宅ケアスタッフだけなので限定されますが、こんなこともあるので油断は禁物です。
また、我が家のように在宅で点滴をしている場合、処置そのものが感染症をまねく可能性もあります。
現に、母は過去2度ポート感染を起こしています。
在宅療養者自身の皮膚に存在する微生物であっても、それらが血管カテーテルなどを伝わって体内に侵入してしまうと、感染を起こすことがあるようなので正しい知識を持って対応していかなければなりません。
感染症を予防するために出来ること
要介護者に、感染症にならないように免疫力をつけさせることができれば苦労しないのですが・・・
そういう訳にもいかないので、介護する側が気を付けるしかありません。
介護者ができることは
- 感染経路を遮断するために、マスク、手洗い、うがい、手袋をする
- ワクチンの予防接種(インフルエンザなど)
- 介護者が病原菌を持ち込まないように、介護者自身の免疫力をつける
調べた限りでは、こんなところです。
感染症を予防するには、介護する側の健康状態もポイントになるので体調管理にも気を付けたいところですね。
おわりに
この10年くらいは、母にうつしてはいけないと思いインフルエンザの予防接種はしていますが、僕は生まれてこの方インフルエンザにかかったことがなく、風邪もこじらせたことがありません。
しかし、退職する前の2~3年は体調ボロボロでした。
インフルエンザこそなりはしませんでしたが、風邪を引くたびにこじらせて病的な感じを認識していたくらいです。
今思えば免疫力が低下していたのだと思いますが、こんな弱った状態で病院に出入りするのは良くないことなんだと知りました。


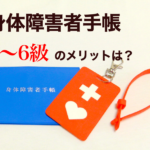






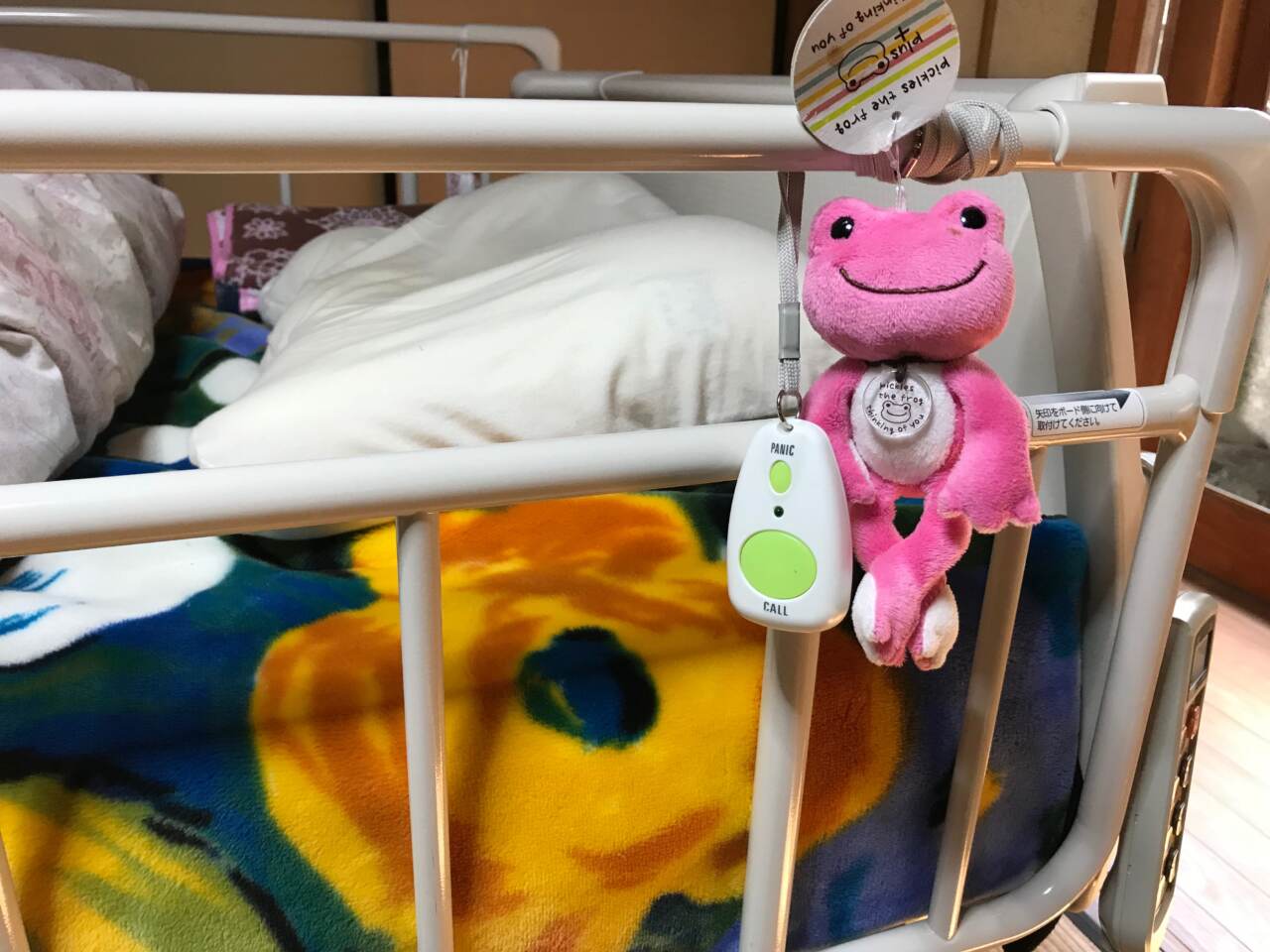





インフルエンザ(飛沫感染)
ノロウイルス感染症(接触感染)
肺炎(飛沫感染)
結核(空気感染)
腸管出血性大腸菌(O157)(接触感染)
尿路感染症(接触感染)
レジオネラ症
MRSA (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)(接触感染)
緑膿菌感染症
疥癬(かいせん)(接触感染)