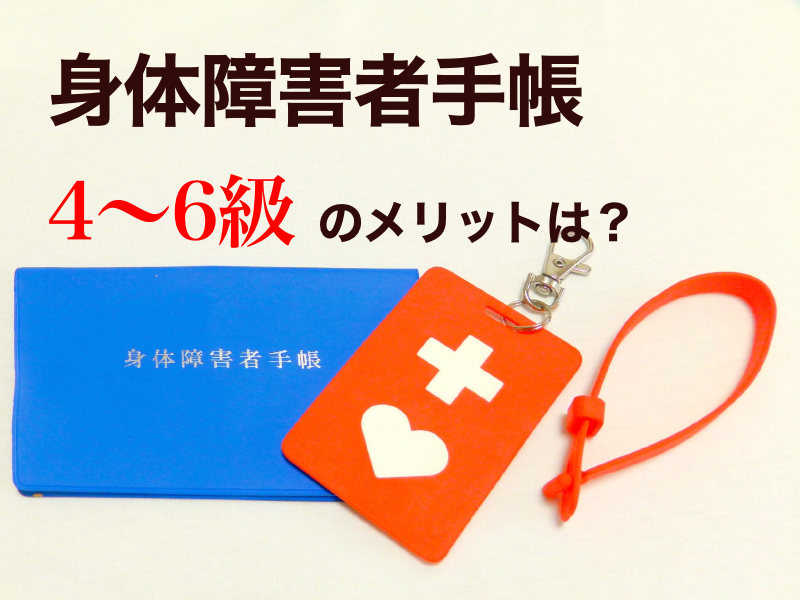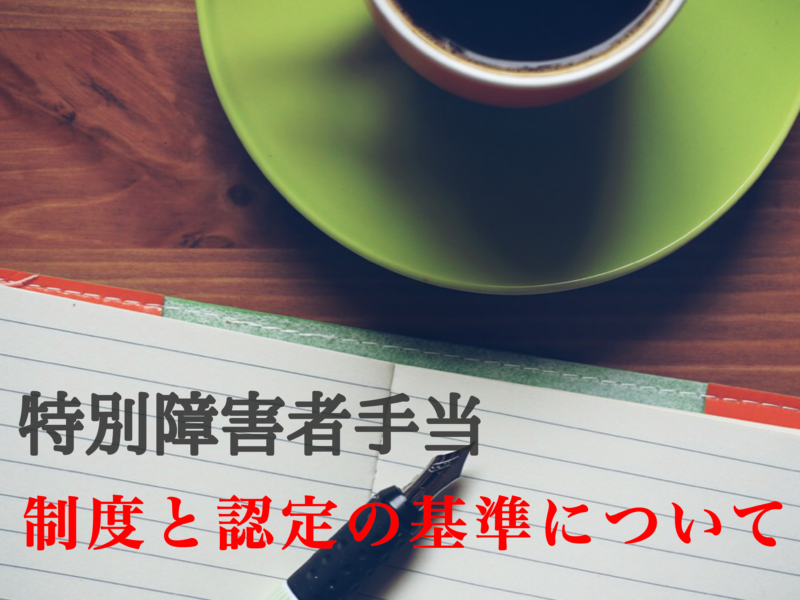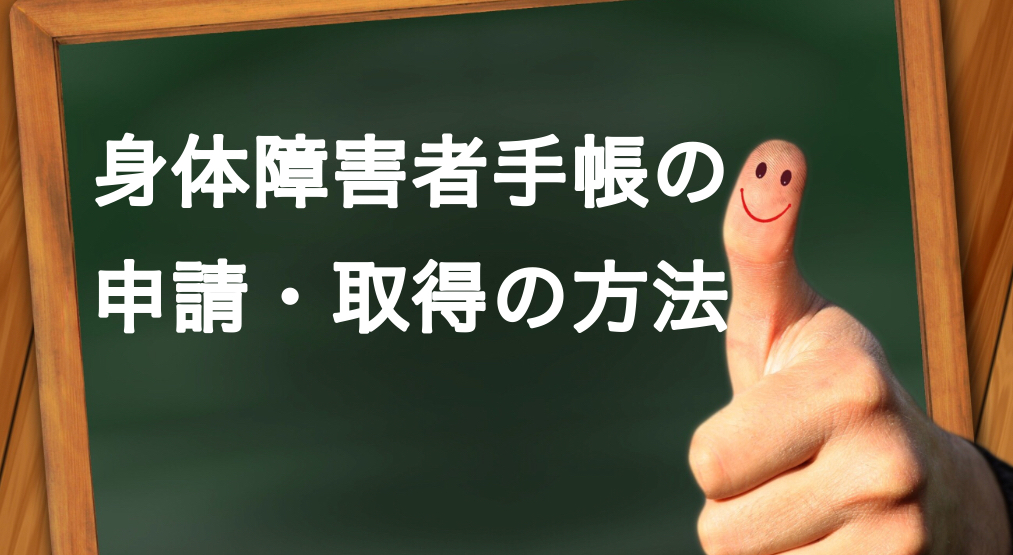消耗品のうえに、継続してかかる紙おむつ。
親に紙おむつが必要になると、その維持費に面食らう人もいるかと思います。
僕も、その一人。
医療費、訪問介護サービス、その次に来るのが紙おむつと、我が家の在宅介護にかかる費用で3番目に多くなっています。
その額、月々7.000~8.000円。
毎年、高価な家電を買えると思うと凹みます。
おそらく、介護をされている方の中には同じように感じられている人も多いのではないでしょうか?
このようなときに、知っておきたいのが紙おむつの給付制度です。
今回は、「紙おむつの支給事業」について解説します。
今は、必要でないご家庭でも来るべき時に備えるべく参考にしてみてください。
目次
「紙おむつの支給事業」とは?
「紙おむつの支給事業」は、在宅で紙おむつを必要とする高齢者を対象に紙おむつを支給する事業です。
その目的は、高齢者を介護している家族の経済的負担の軽減を図ることにあり、在宅介護を支える大切な仕組みとなっています。
下記は、奈良市の要件です。
対象者:65歳以上(要介護認定されている65歳未満の方含む)
奈良市内に住所を有し、かつ在宅で生活している方
要介護4以上の方
本人が市民税非課税及び、同居者全員(世帯分離も含む)が市民税所得割非課税の方。
病院に入院中は不可
支給方法:2か月ごとに現物配達
支給額:1か月3.500円
申請窓口:市役所保健福祉課
介護保険対象施設(介護療養型施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・介護医療院)に入所している方は対象外。
高齢者を入居対象とした施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、グループホーム等)も対象外です。
支給方法については、上限額の範囲内で紙おむつカタログから選択し、限度額を超える分については利用者が負担することになっています。
各自治体の支給要件を比較
他の自治体はどうなのか、ランダムに検索して比較してみました。
対象者:要支援1以上の方
65歳以上で病院に入院している方
介護保険対象施設は対象外ですが、病院・有料老人ホームに入所をした場合は可。
支給額
要支援1・2 1か月3.000円(所得に応じ一部負担金あり)
要介護1・2 1か月5.000円(所得に応じ一部負担金あり)
要介護3~5 1か月7.000円(所得に応じ一部負担金あり)
対象者:要介護4以上の方(一部要介護3を含む)
要介護3は、認定調査票の「排尿」「排便」のいずれかが全介助
病院に入院中の方、施設に入所されている方は対象外
支給額:6.500円
対象者:要介護4以上の方
病院に入院中の方、施設に入所されている方は対象外
支給限度額:年額10万円
対象者:要介護4以上(一部要介護3含む)
要介護認定の認定調査票の「排尿」又は「排便」のいずれかの項目が「全介助」となっている方
病院に入院中の方、施設に入所されている方は対象外
支給上限額:6.500円(かかる費用の1割は自己負担)
対象者:要介護4以上の方
施設に入所されている方は対象外。
支給上限額:
要介護4以上の方・・・年額10万円相当の現物を支給
要介護3以下の方・・・・・年額5万円相当の現物を支給
入院している方には、月額4千円を限度とする現金を助成
比較すると、支給対象者、金額、その他の要件も各自治体でまちまちです。
このように市町村で支給要件がかなり異なりますので、利用を検討している方は事前にお住いの福祉課にお問い合わせください。
「紙おむつの支給事業」は地域格差がある制度
紙おむつの支給事業」は、市町村の独自事業です。
なので、対象者の条件や支給金額は全国一律ではなく地域によって異なります。
ほとんどの自治体が共通している要件
在宅で、65歳以上の要介護認定を受けている人。
世帯全員が、非課税。
あとは、介護保険対象施設(介護療養型施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設)は不可ということくらいでしょうか。
世帯全員とは、住民票上で同一世帯に登録されている方全員を指します。
各自治体で異なる要件
入院中や有料老人ホームに入所した場合でも、紙おむつ代の補助が受けられる自治体があること。
それと、一番大きな差は支給金額です。
他の自治体と比較すればよく分かりますが、奈良市の支給額が良くありません。
奈良市だけでなく、奈良県の他の自治体も1か月3.000~3.500円が相場です。
まあ、地方はどこも財政難。
自治体の財源が反映しており、地方になるほど要件が厳しいのが現状です。
しかしながら、同じ日本に住んでいるのに支給額が倍以上にもなる地域格差に改めて驚かされます。
「紙おむつの支給事業」今後は廃止?
2021年3月末に、役所から来た紙おむつの支給要件の改悪通知の一文。
4月からの支給額を、4.000円から3.000円に減らすというものだったのですが、理由は上記の一行だけ。
一見、それらしい内容ですが、国がどのような制度改正をして縮小に至ったのか、上記の文面から読み取れる利用者は少ないと思います。
まあ、財源がひっ迫している現状、カットされるのは理解できますが、もう少し丁寧に説明していただかないと肝心なことが分からないです。
しかも、紙おむつの支給制度が近い将来廃止されるニュアンスの内容が含まれていましたので気になって調べてみました。
地域支援事業とは
2005年の介護保険法の改正を受けて、翌2006年に創設された介護保険の介護予防事業のことをいいます。
地域支援事業は、市町村で行うもので、介護給付・予防給付とは別に、要介護状態になることを予防し、たとえ要介護状態等になった場合も住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるように実施するものです。
この事業は、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業の3つの事業からなり、「紙おむつの支給事業」は任意事業にあたります。
ちなみに、この支給事業の財源は、国38.5%、都道府県19.25%、市町村19.25%、第1号被保険者の保険料23%です。
「紙おむつの支給事業」が地域支援事業の任意事業から外された経過
2020年11月、翌21年3月のこの経過期間終了前に激変緩和措置として2024年3月末まで延長することを市町村に事務連絡する。
余程、財源が厳しいのか、国が紙おむつの費用負担をカットしたいのが見て取れます。
その結果、2024年4月からは「市町村特別給付」や「保健福祉事業」または市町村独自事業となり財源も変わるようです。
聞きなれない制度や事業名が並びますが、2024年3月末に国からの補助を無くすのであとは各自治体でお願いします。
ぶっちゃけ、そんなところです。
地方への国の補助が無くなれば、財力のある自治体であれば継続するとは思いますが、方向性としては縮小・廃止へ向かうとみるべきでしょう。
しかしながら、国は出費を抑えるために施設から在宅に誘導しているはずなのですが・・・
在宅介護の補助をカットしようとしている現状に、矛盾を感じるのは僕だけではないと思います。
おわりに
今回は、「紙おむつの支給事業」の仕組みを通してこの制度の抱える問題を解説しましたがいかがでしたか?
この制度は、継続の是非は別にして利用者にとってメリットしかない制度です。
たとえ、2024年4月以降に国が手を引いてもすぐに廃止になることはないと思うので、もし要件に当てはまるのにまだのご家庭は申請しておきましょう。
最後に、僕が住んでいる自治体に苦言。
この記事を書くきっけとなった、紙おむつ支給に関する改悪通知が届いたのが3/23。
おむつの枚数の変更提出期限が、3/29までとなっていて唐突過ぎて驚いています。
3月末に通知して4月から縮小変更するなんて、ちょっと利用者への扱いが雑すぎませんか!?
ぺらんぺらんのA4用紙1枚を直前に送付して、改悪が完了するのですから文句の一つも言いたくなります。
しかも、内容が分かりづらい・・・
調べてみると、かなり以前から分かっていたことだけに、せめてもう少し前もって通知して欲しいものです。
こんなやり方は、民間の社会では通用しませんよ(# ゚Д゚)
地域支援事業交付金について(地域支援事業の全体像等)
1.平成30年度以降の激変的緩和措置の取扱い(平成30年3⽉6⽇担当課⻑会議資料p368)
2.介護用品の⽀給に関する取扱(平成31年3⽉19⽇担当課⻑会議資料p450)