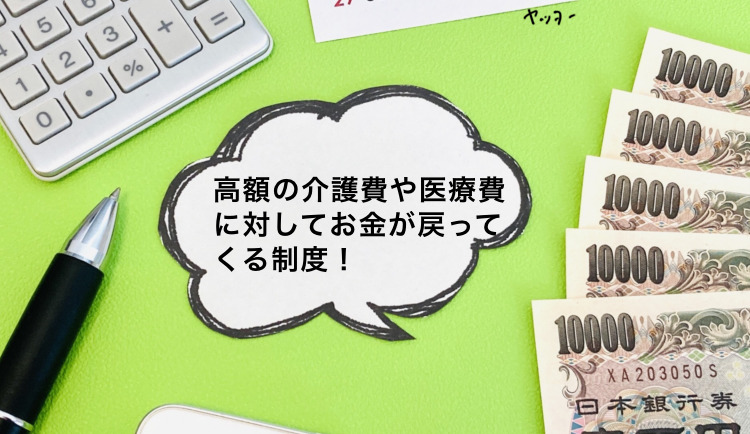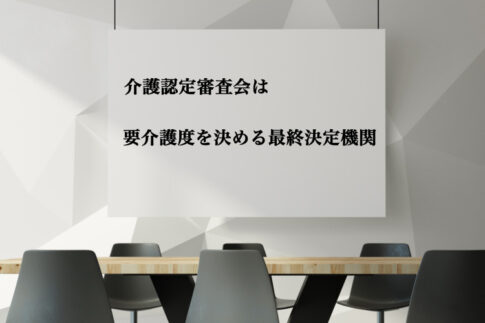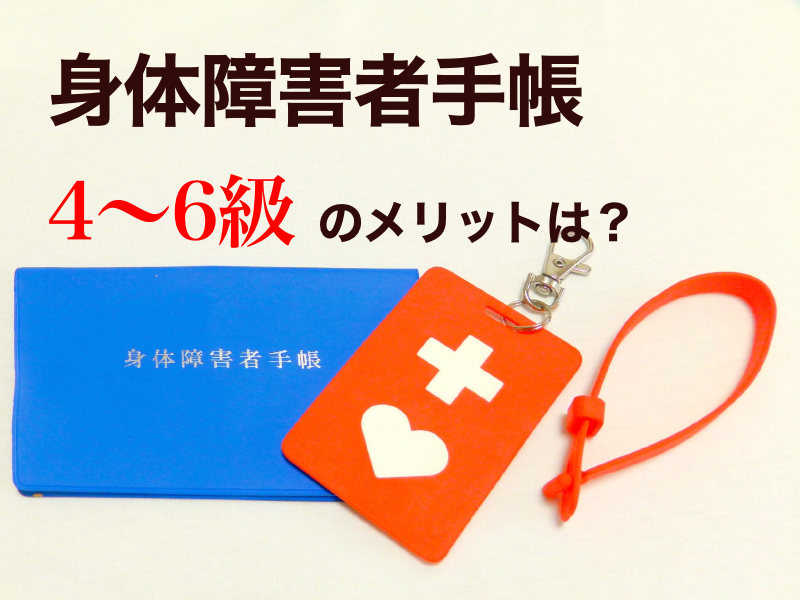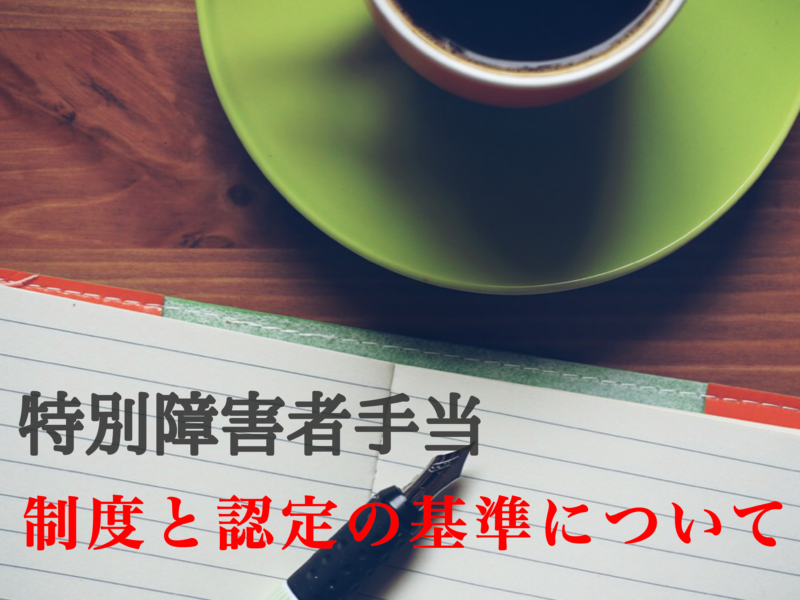在宅介護をされている方の中には、医療費と介護費に金銭的な負担を大きく感じられている人もいるかと思います。
問題となるのは、これらは長期に渡り継続する費用だと言うこと。
それと、一旦利用し出すと減額がなかなか難しいことです。
我が家も、年々増えてきている費用だけに頭を抱えています。
今回は、介護や医療費を軽減する2つの制度について解説しますので参考にしてみてください。
目次
「高額介護サービス費」とは
高額介護サービス費とは、介護保険サービス費の自己負担額が限度額を超えた場合に、申請すれば超えた分が払い戻される制度です。
対象者:要介護・要支援の認定を受けた方
支給対象となるサービス:「居宅サービス」「介護施設サービス」「地域密着型サービス」
対象外のサービス:「福祉用具購入費」「住宅改修費」「施設サービスの食費」「居住費や日常生活費」「支給限度額を超えた利用者負担分」
申請方法:市区町村の介護保険課
申請期限:介護サービスを利用した翌月を初日に2年以内
介護施設サービスは、介護保険施設に入居して受けるサービスのことです。該当する施設は「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4つになります。
高額介護サービス費の対象にならない費用については、ショートステイでの滞在費や施設生活での居住費、食費理美容費など、日常生活に関する実費は対象にはなりません。
対象となる人については、介護保険料を滞納し、給付制限を受けている場合は支給されないので注意してください。
高額介護サービス費の限度額について
限度額を超えた金額が「高額介護サービス費」として介護保険から後日払い戻されます。
自己負担限度額は、以下のように所得によって異なります。
【高額介護サービス費による月額の限度額】(令和3年8月利用分から)
| 区分 | 負担限度額(月額) | |
|---|---|---|
| 市町村民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1,160万円) | 140,100円 (世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円 (世帯) |
|
| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 (世帯) |
|
| 市町村民税非課税世帯 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 (世帯) |
| ・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金を受給している方 |
24,600円 (世帯)15,000円 (個人) |
|
| 生活保護を受給している方 | 15,000円 (世帯) |
ポイントは、世帯全員の利用者負担分を合算した金額が上記の金額を超えた場合に払い戻されます。
高額介護サービス費の計算例
高額介護サービスの払い戻し額は、「自己負担額-負担上限額」で計算できます。
世帯に介護サービスを利用する人が1人の場合
合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方が、1か月の自己負担額が25.000円だとします。
25.000円から15.000円を引いた10.000円が払い戻し金額です。
世帯に介護サービスを利用する人が複数いる場合
世帯に介護サービスの利用者が2人以上いる場合は、全員分の利用料を足してから世帯の負担上限を超えた分を計算します。
仮に、母が50万円分の介護サービスを利用したとして、利用者負担上限額の44.400円にはなりません。
あくまで、要介護5の最大自己負担額の36.217円の枠内での適用となり、介護サービス利用料は青天井とはならないのです。
ちなみに、母の自己負担額は18.865円。
さきほどの表を見る限り、一般的な所得の方の負担限度額は月額44,400円です。
こうしてみると、世帯に2人以上対象者がいないと条件を満たすことができないかと。
そう考えると、そこそこハードルが高い制度と言って良いでしょう。
「高額介護サービス費」支給までの流れ
高額介護サービス費は、支給対象になった際に自治体から申請書が送られてくるケースが多いようです。
申請書に必要事項を記載のうえ、役所などにて手続きを行いましょう。
申請が受理されると、申請時に指定した口座に振り込まれます。
この制度の申請手続きは、初回だけです。
一度申請すれば、後は継続的に払い戻しが行われるので再度申請の必要はありません。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは
高額介護合算療養費制度とは、1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に自己負担額を軽減する制度です。
「高額療養費」「高額介護サービス費」を利用してもなお、一定の額を超えている場合に負担を軽減する仕組みになります。
対象者:医療と介護の両方を利用している世帯
1年間(8月1日〜翌年7月31日)の医療・介護費の合計が限度額を超えた世帯
1年間に支払った自己負担額の合計が、基準額より501円以上払った場合
申請窓口:国民健康保険に加入している人は、市区町村の介護保険課
被用者保険に加入している人は、被用者保険
申請期限:基準日の7月31日の翌日を起算日として2年以内
「高額療養費」や「高額介護サービス費」の対象にならない費用は、この合算制度でも対象外です。
介護費は、福祉用具レンタル料、福祉用具購入費、スロープ設置など住宅改修費、居住費、滞在費など。 医療費は、入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の手術代、高度先進医療費、予防注射など。
算定対象は、世帯単位です。
合算対象は、世帯内の同一の医療保険に加入している場合になります。
70歳以上の人は、すべての自己負担額が合算の対象です。
70歳未満の人の医療保険の自己負担額は、医療機関等ごとに1ヶ月 2万1,000円以上のもののみ合算対象になります。
健康保険、または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象になりません。
すでに払い戻されている高額療養費・高額介護サービス費は自己負担額から差し引かれます。
高額医療・高額介護合算療養費は、自己負担額の比率に合わせて医療保険と介護保険から振り込まれます。
自己負担限度額
高額医療・高額介護合算療養費制度の限度額は、所得や年齢などによって細かく設定されています。
医療保険・介護保険の自己負担額の合計が、これを超えている分が払い戻されます。
| 70歳以上 | 70歳未満 | |
|---|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |
| 年収770万~1,160万円 | 141万円 | 141万円 |
| 年収370万~770万円 | 67万円 | 67万円 |
| 一般 年収156万~370万円 |
56万円 | 60万円 |
| 市町村民税世帯非課税 | 31万円 | 34万円 |
| 市町村民税世帯非課税 (所得が一定以下) |
19万円 |
高額医療・高額介護合算療養費計算例
我が家の場合です。
母の介護自己負担額は、月々18.865円。
医療費は訪問診療と薬代で約18.000円となり、両方合わせると年間約44万円となります。
父親は、介護保険は利用していないので対象外です。
一般だと56万円が自己負担限度額になるので対象にはなりませんが、市町村民税世帯非課税だと13万円ほど戻ってくる計算になります。
ただし、母は身体障害者手帳ですでに控除を受けているので対象にはなりません。
「高額医療・高額介護合算制度」申請の流れ
まず、市区町村に介護に関する自己負担の証明書を取得してから加入している「医療保険」(後期高齢者医療制度、国民健康保険、会社の健康保険など)へ申請してください。
国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している人は市区町村です。
協会けんぽや健康保険組合などは、基本的には勤務先を通してとなります。
- 市区町村に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出
- 市区町村から「自己負担額証明書」が交付・送付される
- 加入している医療保険に「自己負担額証明書」を提出して申請を行う
申請期限は、基準日(原則として7月31日)の翌日から起算して2年以内です。
おわりに
今回は、「高額介護サービス費」「高額医療・高額介護合算制度」について解説しましたがいかがでしたか?
どちらの制度も条件をクリアするには、世帯に2人以上の対象者がいないと利用は難しそうです。
しかし、そもそも医療保険と介護保険によって医療費や介護サービス費の自己負担は1〜3割に軽減されています。
さらに「高額医療・高額介護合算制度」は、「高額療養費」と「高額介護サービス費」を利用しても、なお一定の額を超えている場合の負担を軽減する制度になるので手厚い仕組みだと言って良いでしょう。
もしかして、該当するのでは!?と思われる方は、一度計算して受け取れそうなら迷わず申請しておきましょう。