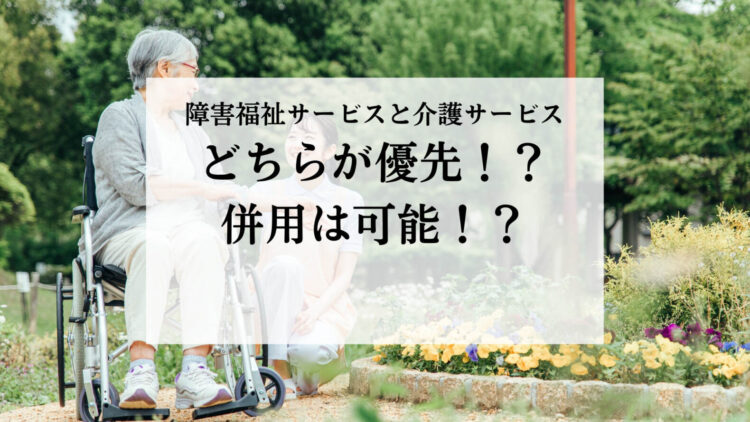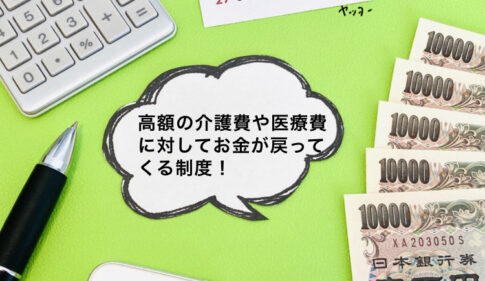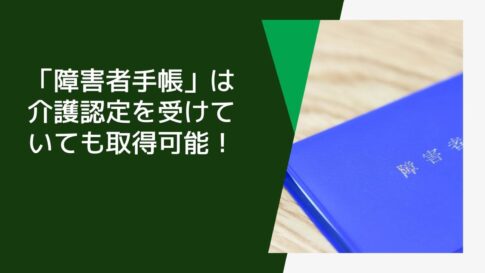皆さんは、「障害福祉サービス」をご存じですか?
おそらく、65歳以降に障害者手帳を取得している方だとご存じない方も多いと思います。
また、知っていても僕のように高齢者の「介護保険制度」と混同している人もいるはずです。
今回は、「障害福祉サービス」とはどのような制度なのか、申請方法、介護保険制度との違い、併用できるかなどまとめましたので参考にしてみてください
目次
「障害福祉サービス」とは
障害福祉サービスは、障害があることで日常生活や社会活動が困難な人に対して支援する制度です。
この制度は、大きく2つの支援に分かれます。
1つは、日常生活に必要な介護支援をする「介護給付」。
もう1つは、自分らしい生活を営むためや就労を行うために必要となるスキルを身につけるための支援をする「訓練等給付」です。
この2つには、支援サービスの種類がたくさんあって目的に合わせて選べるようになっています。

厚生労働省:障害福祉サービスの概要
※対象となる方
対象者は、身体に障害のある方・知的障害のある方・身体障害や知的障がいのある児童・精神障害・難病患者等で一定の障害のある方です。
- 身体障害者(18歳以上)
- 知的障害者(18歳以上)
- 発達障害者を含む精神障害者(18歳以上)
- 満18歳に満たない児童で、発達障害児を含む身体・知的・精神に障害のある方
- 障害者総合支援法で指定されている難病患者(18歳以上)(参考::厚生労働省「指定難病」)
身体障害者を除き、障害者手帳を所持していることは必須要件にはなっていません。
障害者手帳を持っていない知的障害・精神障害や難病等の方でも、障害福祉サービスの対象となります。
支援の内容と対象者の詳細は、厚生労働省の公式サイトでご確認ください。(障害福祉サービスについて)
「障害福祉サービス」の申請方法
サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。
訓練等給付と介護給付では申請手続きが一部異なるのですが、ここでは介護保険制度との類似を焦点にするため介護給付の申請方法を説明いたします。
- 窓口で申請
申請場所は、お住いの市区町村の障害福祉課。
- 認定調査
認定調査員が、心身の状況について本人や家族などから聴き取りをする。
- 一次判定・二次判定
訪問調査に基づき、コンピュータによる一次判定。
審査会による特記事項と医師の意見書をもとに二次判定。
- 認定結果の通知
申請者宛に、障害支援区分認定の結果が通知される。
- サービス等利用計画案の作成と提出
特定相談支援事業者が、サービス利用計画案を作成して市区町村へ提出。
- 支給決定
提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などが支給決定。
医師意見書は、疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見など、申請者の医学的知見から意見を求めるものです。
これは、二次判定において、一次判定を補足する資料として使用されます。
申請から発行まで1~2か月ほどかかるので、必要性を感じたら早めに手続きをおこないましょう。
「障害福祉サービス」の認定調査はどんなことが行われる?
申請後に、調査員から訪問日時の連絡があります。
調査員は、市区町村の職員か市区町村の委託を受けた事業所の人。
いずれも、社会福祉士などの資格を持った専門家です。
調査が行われる場所は、市区町村役場や調査員が働く事業所、もしくはご家庭などで行われます。
認定調査による聞き取り内容は、80項目。
主に、心身の状況や置かれている環境など聞かれます。
所要時間は、調査員のスキルや対象者の状況にもよりますが1時間くらいみていた方が良いでしょう。
厚生労働省のサイトに、認定調査マニュアルがあるのでリンクを貼っておきます(障害者総合支援法における障害支援区分 認定調査員マニュアル)
「介護保険制度」と「障害福祉サービス」の違い

一見、混同しやすい2つの制度ですが、適用される対象者や条件が異なりますので違いを見ていきたいと思います。
|
保険の種類 |
介護保険サービス |
障害福祉サービス |
|---|---|---|
|
保障対象者 |
原則65歳以上(一部40歳以上) |
体に障害のある方(※上記に記載) |
|
認定の必要性 |
必要あり |
必要あり |
|
支援の単位 |
要介護 |
区分 |
|
自己負担額 |
1~3割 |
原則1割 |
|
保障の上限 |
上限あり(利用限度額) |
上限あり(利用者に負担が生じない) |
認定調査の違い
この2つの認定調査の違いは、目的と何が決まるのかを把握しておくと分かりやすいと思います。
介護認定調査は、介護の手間を測ることが目的です。
介護の手間を測ることによって、介護サービスを利用できる費用(介護度・限度額)が決まります。
対して、障害福祉区分認定調査は、障害によってどのくらい支援が必要になるかを測ることが目的です。
それに基づき、市区町村がサービスの種類や量などを決定します。
「介護度」と「区分」の違い
介護保険制度と障害福祉サービスには、それぞれ介護の必要性の程度を表す「介護度」と支援の必要度を表す「区分」で数値化されています。
介護度は、「要支援」1・2と「要介護度」1~5、それに非該当の8段階。
「障害支援区分」は、非該当・区分1〜6の7段階です。
障害福祉サービスは、支援の必要な度合いに合わせて「区分」が決まり、数字が大きくなるほどよりたくさんのサービスが必要になることを表しています。
利用者負担の違い
介護保険の利用者負担は、所得によって利用料金の1~3割。
障害福祉サービスの利用者負担は、利用料金の1割です。
ちなみに、残り7~9割は誰が負担するのか?
障害福祉サービスは、国・都道府県・市区町村が分け合って負担しています。
介護保険は、皆で保険料を負担して必要な人に給付する形をとっているので国民です。
行政ではとても賄いきれないので、財源調達にも違いがあります。
負担額が決まる仕組みの違い
介護保険は、サービスの利用状況で負担額が決まります。
介護度によって、毎月のサービスを受けられる上限額が決まっているので、利用限度額を超える分は全額自己負担です。
対して、障害福祉サービスはサービスの利用量に関わらず、所得に応じて負担上限額が決定します。
しかも、上限を超えることがあっても利用者が負担することがないことも異なる点です。
障害福祉サービスの負担額については、こちらにリンクを貼っておきますのでご確認ください。(厚生労働省:障害者の利用者負担)
有効期間の違い
要介護認定の有効期間は、新規申請は原則6か月、状態により1年が上限です。
更新申請は、原則12か月ですが状態により3年が上限となります。
障害支援区分の認定の有効期間についても、3年が基本です。
ただし、居宅介護等にあっては、利用するサービス量が比較的短期間になることがあるので最長1年間になります。
また、障害者の心身の状況から状態が変動しやすいと認められる場合は、審査会の意見に基づいて3か月以上3年未満の範囲で有効期間を短縮されることもあるようです。
「介護保険」と「障害福祉サービス」はどちらが優先?
障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則として介護保険サービスが優先されます。 (障害者総合支援法第7条)
障害福祉サービスには、上記のように
- 障害福祉独自のサービス(同行援護、行動援護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援など)
- 介護保険と障害福祉の両方の制度に共通するサービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)
2種類ありますが、介護保険優先原則が適用されるのは、2番の介護保険と障害福祉の両方の制度に共通するサービスです。
共通するサービスの例
| 介護保険サービス | 障害福祉サービス |
| 訪問介護(ホームヘルパー) |
居宅介護(ホームヘルプ) 重度訪問介護(ホームヘルプ) |
| 通所介護(デイサービス) | 生活介護(デイサービス) |
| 短期入所(ショートステイ) | 短期入所(ショートステイ) |
| 訪問看護 | 訪問看護(自立支援医療) |
その他にも、下記のサービスは原則として介護保険が優先します。
- 車いすや電動ベッド等の貸与、腰かけ便座・入浴補助用具等の購入
- 訪問入浴サービス
- 施設への入所(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)への入居
- 居宅生活動作補助用具(住宅改修)
これらのように、障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険サービスにあれば、介護保険サービスの利用が優先されます。
介護保険との併用は条件次第では可能!
 基本の優先順位はありますが、利用者の置かれている状況や求めるサービスによっては、介護保険が優先となる方でも障害福祉サービスが認められ併用できるケースがあります。
基本の優先順位はありますが、利用者の置かれている状況や求めるサービスによっては、介護保険が優先となる方でも障害福祉サービスが認められ併用できるケースがあります。
■介護保険には当てはまるサービスがない、もしくは利用者に必要なサービスが障害福祉サービスにしかない場合。
重度訪問介護、先程の1番の障害福祉独自のサービス(同行援護・行動援護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援など)が、これにあてはまります。
重度訪問介護については、必要とする支援が、見守り等の支援、外出時における移動中の介護、病院等に入院・入所している際の意思疎通の支援(入院時コミュニケーション・サポート)等である場合には、介護保険サービスに相当するサービスに該当しません。
■介護保険が優先されることによって、問題が生じるケース。
障害福祉サービスは、65歳になると保険制度移行で直面する問題があります。
- 障害福祉制度と介護保険制度では、上限額が異なるため利用者負担が新たに生じてしまうこと。
- 使い慣れた障害福祉サービス事業所から、別の介護保険事業所を利用しなければならなくなること。
その結果、自己負担額増、サービスの質や量が下がってしまう憂き目に。
このため65歳に至るまで、長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対しては例外的に一定の便宜が図られています。
詳しくは、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。(厚生労働省:介護保険と障害福祉の適用関係)
おわりに
今回は、「障害福祉サービス」の申請方法と、「介護保険制度」の違い、両サービスの併用について解説しましたがいかがでしたか?
国は、若いときから長きにわたって、障害福祉サービスを利用している人であっても介護保険制度を優先させたいのがありありと感じられます。
全ては、財源にかかるからでしょう。
障害のある方に対して、自立支援制度を整えているというのが建前。
介護保険制度に速やかに移行させて、コストカットしたいのが本音です。
そう考えると、65歳を超えてから新たに利用するには、よほど深刻な要介護状態でないかぎり認定に個人差が生じると考えておいた方が良いかもしれません。
障害福祉サービス適用の可否や両サービスの併用については、担当するケアマネジャーが作成するケアプランに基づき、お住いの市区町村が判定をします。
利用を検討されている方は、ケアマネジャーや市区町村の福祉課に相談してみてください。